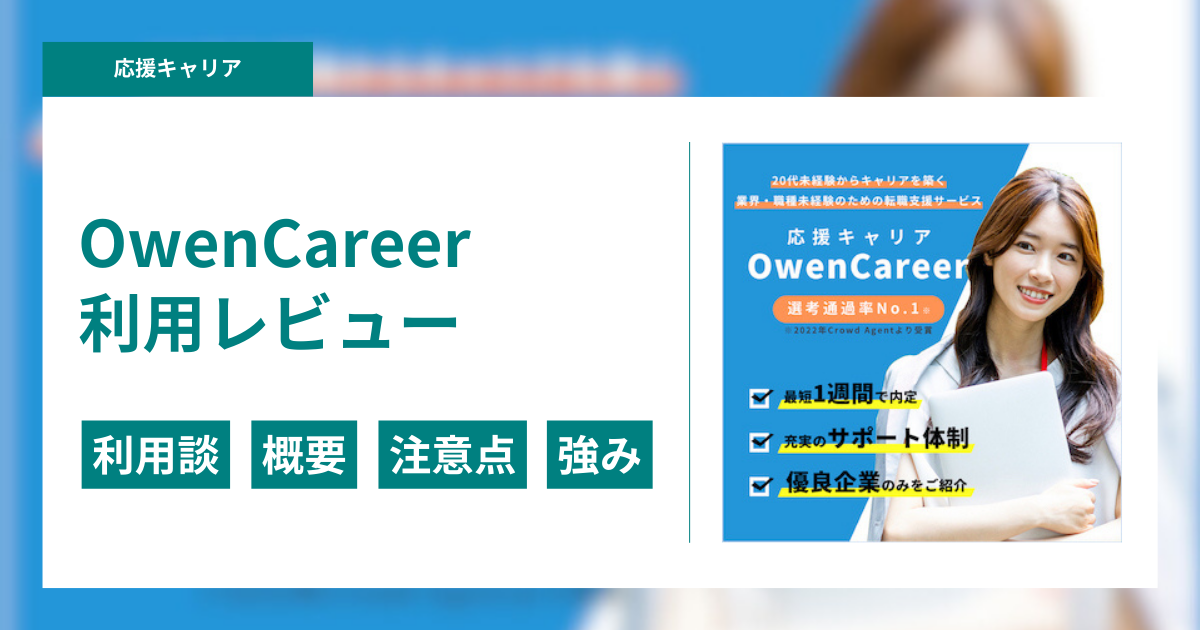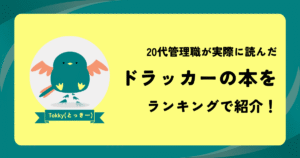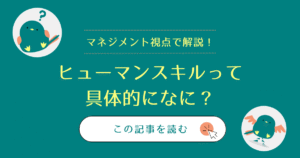この記事でわかること
- マネジメント業務で気を付けていること
- マネジメント業務で気を付けた方がいいこと
- マネジメントで覚えておくと便利なコツと知識
組織やある会社でキャリアアップを目指して日々精進している方が必ずといっていいほど通る道として、マネジメントがあります。
 Tokky(とっきー)
Tokky(とっきー)Tokky(とっきー)もキャリアアップを目指して日々精進した結果、社会人半年でSV(スーパーバイザー)という役職がつき、また2年目でマネージャークラスの業務をこなすようになりました。
当然、そんな自分が日々のマネジメントの業務で意識していることや気を付けていることがたくさんあります。
意識している/気を付けていること
- 余計な業務や問題を増やさないためには?
- きちんと目標や情報を整理/管理するためには?
- 現場や部下の人たちが困らないようにするためには?
- どうすればもっと効率よく人が動かせるのか?
これもある意味マネジメント業務の一環ではありますが、それぞれでしっかり気を付けてさらに組織をよくして成果を上げようと日々奮闘しています。



もちろん、自身のマネジメントスキルを向上させることも兼ねています!
自分と同じく上のキャリアを目指して就職活動や転職活動をしている方にとって、マネジメントのコツは先に知っておきたいですよね。
今回はそんな方に向けて自分がマネジメントで日々気を付けていることなどについてお話ししていきます。



前提である「マネジメントの定義」と「自身の業務内容」については、以下の記事で詳しく話しているため、こちらを参照してみてください!
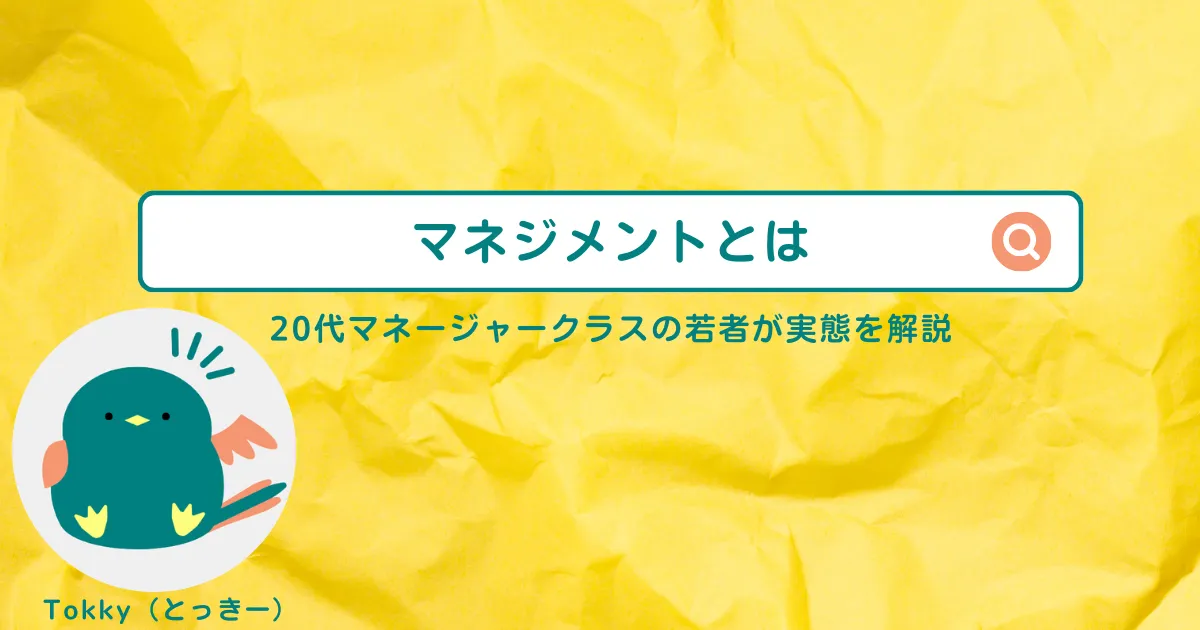
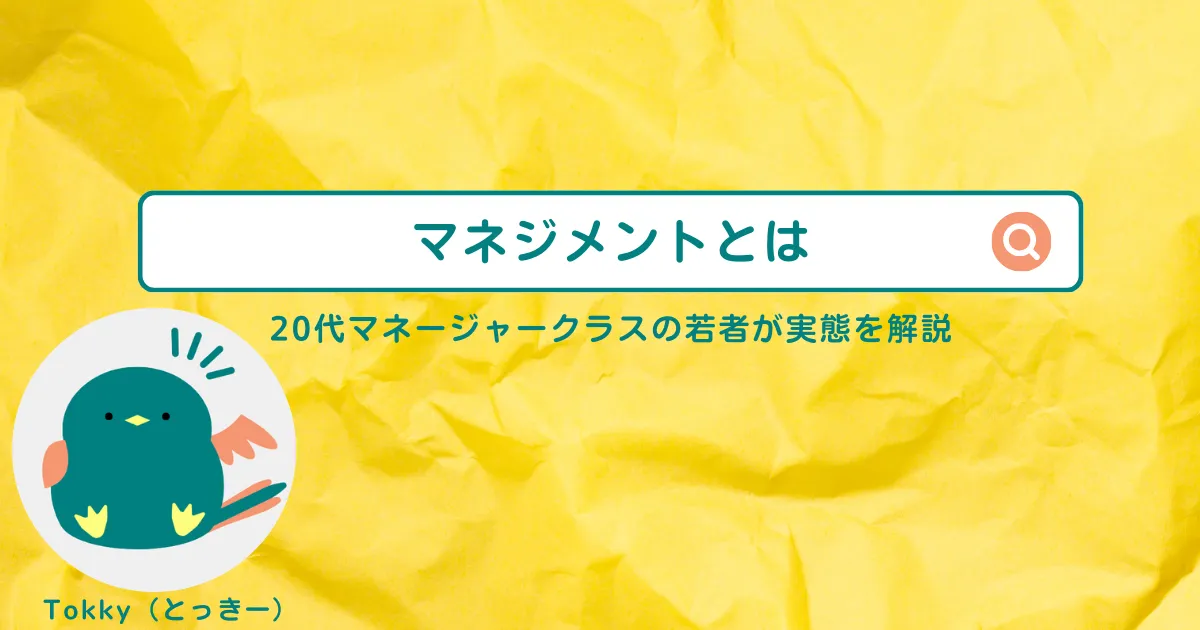


マネジメント業務で気を付けていること



今回はマネジメント業務について以下の観点から話していきます。
- 普段気を付けていること
- 行う際に気を付けた方がいいこと
- ちょっとしたコツ
全体
まず、マネジメント業務全般でいうと、マネジメント業務を構成する各業務が互いに相関できているかということに気を付けています。
各業務はそれぞれ独立して成立しているわけでなく、他の業務と連動して成立しているところがあります。
例えば、評価管理は部下への動機付けを用いるための制度、または組織の目標または指標を因数分解したうちの一つとしてつながっている部分があります。



鶏が先か卵が先か、そもそも何が鶏で何が卵なのかという少し難しい話にもなってきますが、互いの要素をしっかり組み合わせないと矛盾点が生じます。
言い換えれば、ある一つの業務の組み合わせないでズレが生じれば、組織全体の設計または動きがずれていくということです。
そして、結果として大きな問題やトラブルともなり、下手をすると組織全体が成り立たなくなって崩壊を招く恐れがあります。



そのため、普段から各業務でしっかり矛盾点がないように一貫した設計および内容になっているか気を付けています。
そして、このズレは組織運営における問題やトラブルの解決、または最適化や活性化のためにカイゼンをするための修正をしたときによく起こりがちです。
よって、一ヶ所でも修正したら他の業務もしっかり見直すといった全体を見渡すまたは把握することが大切です。



加えて、全体が一貫して矛盾点が生じないためには、各業務でもしっかり気をつけておかなければならないポイントがあるため、一つずつ細かく見ていきましょう。
組織運営(チームマネジメント)
まず、組織運営において気を付けていることは、理念やコンセプト、役割など組織運営の軸になる要素を頻繁に変えないことです。
そもそも、コンセプトや理念などの人の価値観や考え方から来るものは、頻繁に変えられるものではありません。
加えて、コンセプトや理念などはトップマネジメント層が決めた組織文化や価値観を構築する重要な役割を担っています。
そのため、その組織やチームが会社の一部分だけであっても、会社における他の組織にも影響を及ぼす可能性があります。
仮に人の価値観や思考を変えようとする場合、基本的に最低6ヶ月の期間を要することになります。



こちらの理由はまた別記事でお話しします!
言い換えれば、仮にコンセプトを変えて掲げたとしてもそれが部下に浸透するまでに6ヶ月以上の月日がかかることになります。
「全体」で気を付けていることで述べたように、各マネジメント業務は互いに連動しているため、他の業務もそれに合わせて修正していかなければなりません。
このようなことから、特に形にするまで時間がかかるコンセプトや理念、社内の役割は頻繁に変えない方が賢明です。



さらに、チームビルディングから組織運営を行う際も、コンセプトや理念はしっかり考えておいた方がいいです。
もちろん、時と場合によって変更しなければなりませんが、むやみに変えることはかなり重労働を強いられることになります。
目標または指標の設定
組織運営や動機付け、評価管理など様々な業務につながってきますが、組織のコンセプトや人的資本の性質を考慮することに気を付けています。
例えば目標を高く設定しすぎて現実と乖離がある場合、他の要素も絡んできますが、基本的に人を動かしにくくなります。
なぜなら、施策に対してどんなに頑張っても目標を達成できないという結果が明らかに分かると人はストレスなどから動く必要や気力がなくなるからです。
通常、組織における人は目標を達成するために頑張ってその達成感や評価または対価を得るというのが原則です。
この原則より、自分の考えと行動に矛盾点が生じることでストレスや不快感を感じさせることになり、また人の心理的傾向から動きにくくなるということです。



ちなみにこれは行動経済学や心理学の分野である「認知的不協和」という心理的傾向が関係しています。
また別記事でお話するため、参考にしてみてください!
しかし、これを恐れて目標を低く設定しすぎてしまうと、本来は目標以上の成果を生める部分が損失となってしまうこともあります。
これは、与えられた成果や評価を得ることが動機になっている場合、それ以上動く必要がなくなってしまうためです。



よく学生時代のレポートや課題を提出する際に「間に合えばいいや」とか「単位だけもらえればいいや」とかいうことに近いですね。
確かにそれでもいいのですが、組織上ではこのことは機会損失につながります。
よって、目標設定を行う際は、特にその人の性格や動機などを正確に把握しておくことが重要となります。
そして、これを把握する手法として、部下と定期的に1on1ミーティングを行うなどがあります。
他方で、当月の目標設定を行う際には先月の振り返りに引っ張られすぎないことにも気を付けています。
日本には四季が存在していることや、月によってはクリスマスなどのイベントが発生するため、当月も先月と同じ傾向になるとは限りません。
先月の振り返りというのは当月の外部環境・内部環境などの分析を正確にするために行う業務です。
先月がこの数値だったから今月はこの数値になるといった断片的な情報だけで目標または指標を設定しないように心がけています。



行動だけでなく、このような分析でもバイアス(偏り)が生じます。
これについても別記事でお話ししていきます!
人材管理
人材管理で一番気を付けているポイントは「教育」です。



正直、教育がすべてと思っているくらいに大切にしており、またその中で特に採用してから一番初めの研修に一番力を入れています。
なぜなら、その研修内容がその人にとってのアンカーまたは基準となるため、今後にかなりの影響を及ぼすためです。



行動経済学の分野では初頭効果やアンカリング効果などと言いますが、第一印象で決まったものを変えることはかなり困難です。
加えて、その人の視点でいえば慣れない環境や分からないことが多いことから緊張や不安な気持ちを抱いている人がほとんどです。



今の時代ではシビアな内容ですが、人という動物または脳の生物的構造上、特に女性はこのような気持ちに影響が出やすい傾向があります。
しかし、逆を言えば何も知らないことやその気持ちを解消するために覚えなければならないという意識が強い状態でもあります。
そのため、初めの教育は印象付けや基準作り、さらには組織に対するロイヤルティ※をつけるには重要なポイントなのです。
ロイヤルティとは
あるものに対する忠誠心のようなものをが生まれるという心理状態のことです。
しかし、新人メンバーに気を取られすぎてしまって既存のメンバーや部下との関係構築を怠ってはなりません。
確かに新人の研修・教育は重要ですが、だからといって既存の部下に対して何もしなくてもいいわけではありません。
2つとも行うのはとても大変ですが、既存の部下ともコミュニケーションを取って関係性の維持・または向上を測っていかなければなりません。
このとき、メンバーにも新人教育のサポートをしてもらうと、双方が捗る上によい心理効果がたくさん期待できます。
しかし、オペレーションやルール、価値観などがしっかり統一されている状態でなければ返って悪影響を及ぼします。



さらに、採用に関しても気を付けているポイントがありますが、また別の機会にお話しします。
評価管理
評価制度に関しても、組織のコンセプトや理念、部下やチームメンバーの属性などを考慮して妥当性をもたらすことに気を付けています。
まず、評価制度が組織のコンセプトや理念と異なっている場合、メンバーに対して正当な評価が与えられず、またそのことで人材管理などに影響が出ます。
加えて、メンバーの行動指針や組織の文化形成などにも影響を及ぼすことになってしまうため、設計やカイゼンでは気を付けた方がいいです。
さらに、評価制度の設計構築およびカイゼンにおいて気を付けた方がいいポイントとして、自身と部下の視点が異なっていることがあります。



ここも現代ではシビアな内容ですが、生物的に男性は結果を重視する思考が強い傾向であることに対して、女性は過程を重視する思考が強い傾向があります。
他方で、メンバーは目標や評価といった指標ではなく、プレイヤーとして業務に焦点を合わせていることが多いです。
これも含めて、視点の違いを考慮しないと「こんなに頑張っているのに全然見てもらえてない…」などと動機に支障が出る恐れがあります。
加えて、「この人は自分のこといつも見てないんだ…」「わかってない…」などと思われてしまい、信憑性など人間関係にも影響を及ぼす可能性があります。
よって、評価管理の面も含めてマネジメントにおいて、組織としてのマクロ的視点からプレイヤーとしてのミクロ的視点の広い視点を持つことが大切です。
動機づけ
動機づけを行う場合で気を付けていることは、部下の心理的状況に左右されずにこちらがコントロールすることです。
動機づけというのは、部下に対する心理的アプローチを行って人を動かすことであるため、部下の心理状況が軸になります。
ここで、こちらが部下の心理状況に寄り添いすぎたアプローチをすると自身が想定した通りに動かせなくなってしまう恐れがあります。
そもそも、心理や気持ちといった内面要素は一過性の性質が強く、また限定合理性を持ち合わせています。
そのため、部下の気持ちに寄り添いすぎると、人を動かすというよりも自身が部下に振り回されることになります。



つまり、ある意味合理性を追求した非情な面も持ち合わせなければならない時もあるということです。
しかし、だからといって部下の心理状況を全く無視したアプローチをかければそれもそれで部下は動きません。
よって、しっかり部下の心理状況や行動原理を把握して、適切な心理的アプローチを行って成果を生むように動かしていく必要があります。



ここで、合理性を追求した経済学と人間の心理を追求した心理学を併せた行動経済学という分野が非常に役立ちます!
(まあそもそも論として、動機づけより、どちらかというと自然に人が動くような仕組みや構造の方が重要だと思っている人なのですが…)
その他
その他には、自身で新しい付加価値の創出や知識またはスキルの獲得ができるように、ワークショップ型の組織を作ることを心がけています。
従来のトップマネジメント層が下した課題に対してミドルまたはロワーが解決を図るトップダウン式の上下関係がはっきりした組織図をファクトリー型といいます。
これに対して、ワークショップ型の組織とは、メンバーが柔軟に協力しながら課題解決を進めるために創造的な対話や協働を重視する組織形態です。
そのため、この組織構造ではメンバー内の関係がフラットになることからある程度の権限もメンバーに落とすことになります。
もちろんデメリットもありますが、このことで新しいアイディアが浮かびやすくなり、また自身の業務も部下やメンバーに落としやすくなります。
そのことで、人材育成や付加価値の創出、新しい知識とスキルの獲得などの実践とそのきっかけを多く作ることができるようになります。



正直会社や自信の裁量権など外的要因によって左右されますが、近年においてこの考えや組織図は注目されています。
ここも抑えておくといいいです。
まとめ



なんとなくマネジメントで気を付けた方がいいことは分かりましたか?
以下に今回の記事の要点をまめておきました。
<Tokky(とっきー)がマネジメント業務で気を付けていること簡易表>
- 全体
-
マネジメント業務を構成する各業務が互いに相関できていること。
- 組織運営(チームマネジメント)
-
理念やコンセプト、役割など組織運営の軸になる要素を頻繁に変えないこと。
そして、組織のコンセプトや人的資本、特にいえばその人の性格や動機などを正確に把握しておくこと。
- 目標または指標の設定
-
組織のコンセプトや人的資本の性質を考慮し、また当月の目標設定を行う際には先月の振り返りに引っ張られすぎないこと。
- 人材管理
-
新人メンバーの教育と、それに気を取られて既存のメンバーや部下との関係構築を怠らないこと。
- 評価管理
-
組織のコンセプトや理念、部下やチームメンバーの属性、さらには自身と部下の視点が異なっていることなどを考慮して妥当性をもたらすこと。
- 動機づけ
-
部下の心理的状況に左右されずにこちらが部下をコントロールすること。
- その他
-
ワークショップ型の組織を作って人材育成や付加価値の創出、新しい知識とスキルの獲得などの実践とそのきっかけを多く作ること。



他にも日々のマネジメントでは様々なことに気を付けて業務をこなしています。
それほどマネジメントは奥が深く、またこれに伴いマネジメント業務には楽しい一面と難しい一面があるのです。
はじめは難しくて大変かと思いますが、自分で型を見つけて定めていけば簡単に楽しくなっていきます。
しかし、実際にやってみないと大変さや楽しさというのはなかなか実感が湧かないかと思います。



そこで、下記の記事で「実際に管理職になってどうなの?」ということに関して、本音でお話しています。
こちらも続けて読んでみてください!