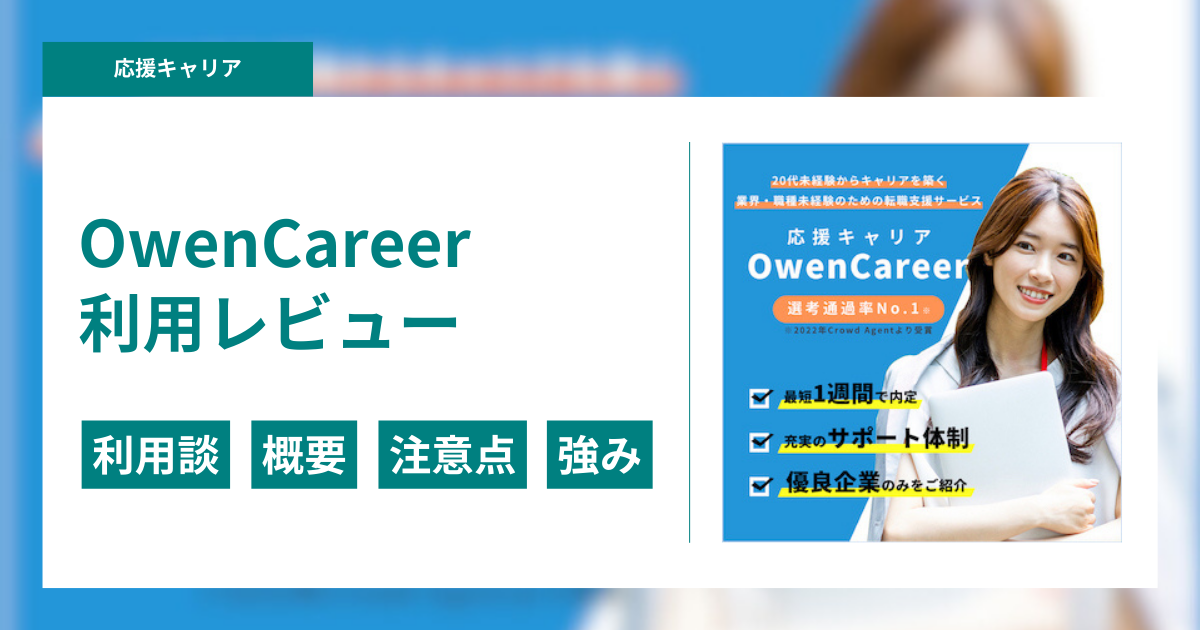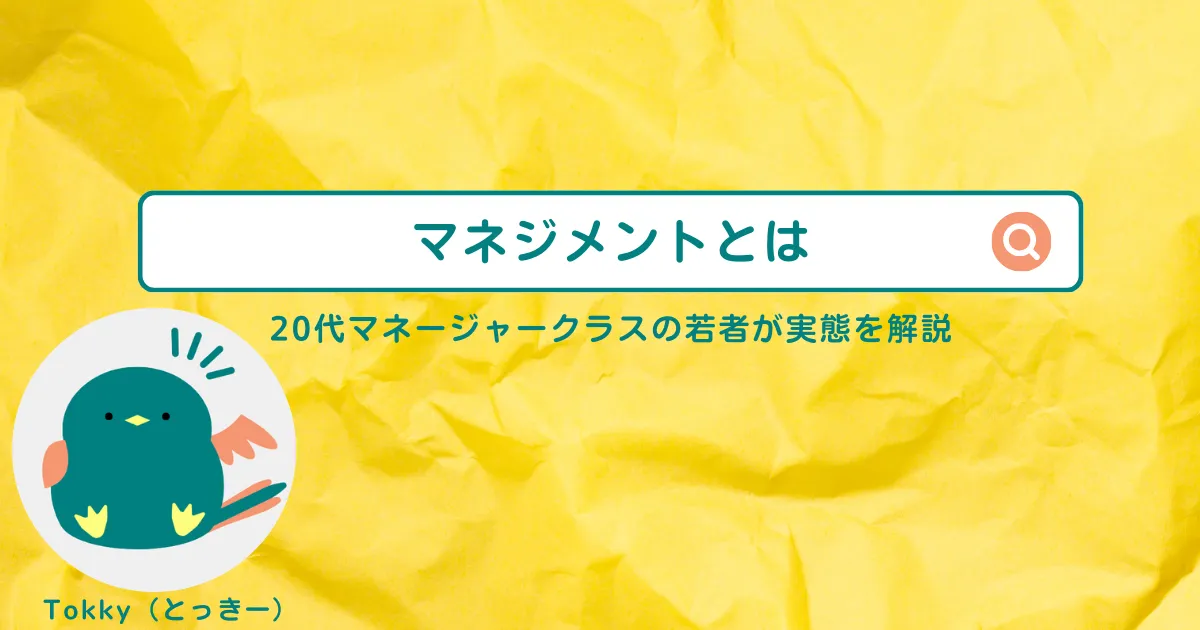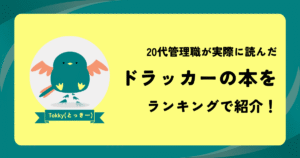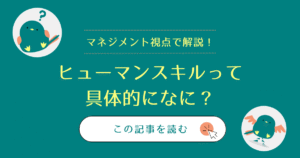この記事でわかること
- 実際に管理職は楽しいのかつらいのか
- マネジメント層になってどうなのか
- マネジメント業務で楽しいこと/つらいこと
 Tokky(とっきー)
Tokky(とっきー)世間の大半の方がこう思っているのではないでしょうか。
具体的には、
- 「管理職になると労働時間やばそう」
- 「働いてばっかでプライベートなさそう」
- 「なんかよく病むって聞くけど」
- 「めっちゃブラックそう」
…など、こんなことを思っているのではないでしょうか。
現代では働き方改革やそれに伴う労働法の改正によってワークライフバランスがかなり重要視されるようになりました。



こういったことも踏まえて、「マネジメントをしてみたい」「管理職になってキャリアアップしたい」と思っても内心踏み出せない人も多くいるのではないでしょうか?
さらに、人や環境によってはなかなかこのことに共感してもらえないということもあるのではないでしょうか?
キャリアアップをしてマネジメントを始めた、管理職になったという方の中にはいきいきとやっている方ももちろんいます。
さらには、そのおかげで仕事面だけでなく、お給料もプライベートも充実して毎日が楽しいなんて方もいます。
そういったことで、
「管理職ってぶっちゃけどうなの?」
ということを20代でマネジメントを行っている者が赤裸々に話していきます!
マネジメント層になって思うこと
まず、結論からいうと…



実際にこう思った理由や根拠について話していきます。
楽しいポイント
マネジメントをやっていて楽しいことは、成果目標を達成するために自分である程度考えて実践したものが成果として形になっていくことです。
特に、自分で試行錯誤しながら最終的に目標の成果物を生み出す組織を形成していく過程にとても楽しさを感じています。
ミドルまたはロワーマネジメントでは、基本的にトップマネジメント層が決めた戦略や方針を現場に実行可能な形に落とし込むことが求められます。
そのため、トップマネジメント層の戦略や意図を正しく理解してどうやって形にしていくか自分で考え実践する必要があります。
その過程でもちろん大変な部分もありますが、その分それを乗り越えたときの達成感や経験は自分にとって大きな糧となります。
加えて、自分で考えて実践するところにある程度の自由や裁量が認められるため、多少の融通を利かせることもできます。
情報や知識のインプットとアウトプットができるため、挑戦や学習を通じて自己成長を感じることが多い点も楽しさの一つとして挙げられます。
そういったことを踏まえて、自分で考えて実際して最終的に成果を上げていくことが楽しいです。



後ほど詳しく話していきますが、メンバーと協力し合えるということも楽しいポイントとしてあります。
マネジメントの楽しさはある意味作品作りや職人と近い部分を感じます。
つらいポイント
一方で、ある組織において双方の意見の食い違いの間にいる場合は精神的にかなりつらく感じることがあります。
双方の意見が食い違うとまとめることが難しく、また感情面や人間関係の要素が入ってくるとさらに複雑化していきます。



正直、「そんなこと知らんがな」って思う時もありますし、「自分を挟まず直接やってくれないかな」などいろいろ思う時があります。
しかし、そんな自分の考えや思いと現実は異なり、そういったことも踏まえて自分にとって理不尽なことが増えていきます。
そういったギャップや結果からストレスや精神的負荷がかかり、一人で頭を抱えるまたは悩んでつらくなってしまう部分があります。



ちなみに、ストレスとは、現実と自分のイメージのギャップを指します。
他方で、自分や現場の意見が正当にミドルまたはトップに伝わらずに成果が目標できなかったということもつらく感じます。



別記事で解説しますが、人は自分が何のために頑張っているのか分からなくなったときに精神を病みやすいと言われています。
そのことも踏まえて、理不尽に自分の意見が通じずに最終的に成果が達成されないと現実と自分のイメージのギャップにつらさを感じます。
これに付随して、トップまたはミドルマネジメント層の意見しか通用しない場合、自分の存在意義が薄くなることにもつらさを感じます。
各マネジメント業務で思うこと
このことを、以下のTokky(とっきー)の日々の業務における楽しいポイントとつらいポイントの2点から細かく分けて紐解いていきます。



各マネジメント業務の詳細は以下の記事で読んでみてください!


組織運営で思うこと
組織運営では、
と思います。
組織運営の業務に関して、楽しく思うポイントとつらいと感じるポイントは以下のようなものがあります。
| 楽しいポイント | つらいポイント |
|---|---|
| 自分やメンバーの案を反映させやすい。 自分が築き上げたものに資産性を感じられる。 自分一人ではできないことができ、またその分大きな成果を上げることもできる 達成感や自信といって成功体験や自己成長を強く感じることができる。 | 裁量権がない、または自分の意見が正当に通じない場合、組織のほぼ言いなりまたは意思のない操り人形のようになって自分の存在意義が分からなくなる。 自由が認められる一方で責任が伴う。しかし、会社やメンバー、状況次第では自分の自由が認められない上に責任だけ負わされる場合がある。 |
楽しいポイント
第一に、成果を達成するために自身の裁量によって自分やメンバーで考えた案がある程度反映させることができる点が楽しいです。
基本的に、社会生活では倫理や法律など、業務や仕事ではその組織の規則や環境など決まりにしたがって普段やっていますよね。
そんな中で誰しもが必ずといっていいほど一度は思うこと、



例えば学生生活では髪染めちゃいけないとか、社会人では特に必要ないのに朝9:00に出勤しないといけないなどありませんか?
マネジメントでは、それが成果目標の達成につながらない非生産的な要素だと判明すれば自分で変えることができます。
第二に、成果目標達成のために自分で組織を組み上げていくため、それが自身の財産や資産と感じることも楽しさの一つです。
特にチームビルディングではチームというメンバーの集まりを自分を中心に形作っていくため、実際に視認できるところに資産性を感じます。
最後に、チームビルディングや資産性ということに付随して、自分一人では上げられない成果を上げることができる点も楽しさの一つです。
メンバーをうまく動かすことによって自分一人で行うより大きな成果を生み、またそのことでメンバー含めて達成感を得られることができます。
加えて、達成感といった成功体験は自信にもつながるため、自己成長を感じ取れることも楽しさややりがいとして挙げられます。
つらいポイント
一方で、組織運営においてつらいポイントとして、自分の意見が正当に反映されずに組織の言いなりになっている場合があります。
人によっては何も考えず言われたことをするだけだから楽だと思う人もいますが、単純に自分で考えて実践できるという楽しいポイントがなくなります。
加えて、組織に関係するメンバーの中で意見に乖離がある場合、それらを収拾するのにとても精神的にも肉体的にも負担がかかってつらい部分があります。
さらに、こういった中では、組織内の問題のカイケツやトラブルが発生した際の責任だけなすりつけられる場合もあります。
もともと、自由が認められるということはその分責任もついてくるということでもあります。
言い換えれば、この原則に則ればマネージャーなどの責任者にはその分の自由が認められているということでもあります。
しかし、この原則が通じずに自由が認められないのに責任者としての責任を負わされるということは、理不尽さを感じます。
加えて、このことは自分が都合よく扱われているとも感じるため、組織における自身の存在意義がわからなくなります。



社会に出ればそんなこと当たり前という人もいますが、正直こういった面は精神的にきつく感じる部分はあります。
目標または指標設定で思うこと
目標または指標設定では、
と感じます。
細かい部分でいうと以下のような内容になります。
| 楽しいポイント | つらいポイント |
|---|---|
| 自分の分析や仮説が正しいかPDCAサイクルができること。 数字や指標を通して組織全体を見渡して把握できること。 先のことを推測していくため、未来を読む力が身に着けられること。 目標を達成することで成功体験と実績がつけられること。 多くの情報や知識を手に入れられやすいこと。 | 目標達成のために自身で調整などができないとズレが生じてマネジメント業務が一貫しないこと。 |
楽しいポイント



正直、個人的には分析や数字管理はかなり好きなのでこの業務そのもの自体は楽しく感じています。
自身のマネジメント業務において、目標設定はPDCAにおいてP(Plan:計画)とC(Check:検証)にあたる業務です。
そして、この目標を実際に達成するためにPDCAのD(Do:実行)とA(Action:改善)の要素を担うのが主に組織運営をメインにしたその他の業務になります。
つまり、目標設定はあらゆるマネジメント業務の軸になるため、これを通じて組織を動かしてカイゼンして成功体験と実績を積むのが楽しいです。
そして、目標設定では組織全体を見渡す必要があるため、多くの情報や知識を把握していなければなりません。
そのため、自然と多くの情報や知識が集まりやすくなることから多くのことを学ぶことができます。
さらに、目標設定では必ずいくつかの将来における不確定要素を推測していかなければならないため、自然と長期的な視野と先を読む力が身に付きます。
このようなインプットとアウトプットを頻繁に行うことから自己成長の場としては最適な環境とも言えるため、そこに楽しさを感じます。
つらいポイント
しかし、自身である程度できないと他のマネジメント業務と一貫性がなくなってしまうことからつらく感じる時があります。
まず、マネジメント業務はある程度相関していなかれば、矛盾が生じて互いの業務に支障が出てきてしまいます。
特に、目標設定は各マネジメント業務の中心となっているため、目標設定のズレはマネジメント全体にかなり影響を及ぼします。
このことから目標設定は他の業務のことも考えて行っていくため、他の業務において自身があまり関与できないと計算や算出がその分難しくなります。
つまり、目標設定の楽しさがなくなって自己成長の場を失うということになるため、自分も含めた機会損失を強く感じる場合があるということです。
逆に自身で目標設定が自由にできないと、「いや、そこまでは現実的に難しいだろ…」とハードルが上げられるという場合もあります。
人材管理で思うこと
人材管理では、
と感じます。
楽しく思うポイントとつらいと感じるポイントは以下です。
| 楽しいポイント | つらいポイント |
|---|---|
| 自分で採用すると研修や教育、関係性の構築などの業務が一貫することからやりやすくなること。 自分で採用した方がロイヤルティ※をつけやすいこと。 採用から行うとその分の知識やノウハウを手に入れられること。 | 採用まで自分で行うとその分の業務量や幅が増えて負担が大きくなること。 人事部や担当者が別で採用を行っている場合、双方と連携がうまくできていないとズレや食い違いが生じてうまくいかなくなること。 人間関係の問題に巻き込まれやすいこと。 |
楽しいポイント
特に人材採用の業務において、その業務を自身で担えると他の業務と一貫して行えるため、視野が広がって楽しく感じます。
各会社や組織の形態などによって大きく変わりますが、中小規模であれば、面接において面接官である自分が応募者にとっての会社の印象になります。
言い換えれば、応募者の判断基準は自分の印象とほぼ等しくなるため、自分について行こうと思えるかどうかが応募者の判断基準に含まれます。
つまり、採用から行うことで教育や研修、関係構築などにおいてこの潜在意識を拾ってあげやすくなるということです。
加えて、そのことで自分に対するロイヤルティを形成することにもなるため、自分の存在意義や成果を生み出していることを実感しやすくなります。
さらに、自分で採用まで行うことで採用における知識やノウハウまで得ることができるため、自身の可能性を広げることもできます。



人事としての道もいけますし、起業して組織を拡大していきたい、あるいは転職したい時など様々な場面で大いに役立ちます。
つらいポイント
しかし、採用まで行うと業務量や業務の幅が大きくなってしまい、その分の負担が大きくなるということはつらいポイントとして挙げられます。



特に最初の慣れていない頃や型ができていない時は、型の作成や慣れるまでに苦労を強いられることがあります。
ビジネス形態でいうと、垂直統合か水平統合かというような考えに近いですね。
一方で、特に大手企業など組織や労働資本が多い会社では、採用は主に人事部など別担当者が行っていることが多いです。
そういった場合、その人事部や担当者との情報や考えに非対称性が生じると、その分採用後のマネジメント業務に支障が出ます。



特に現代において考えや価値観などは仕事や人間関係において重要な要素の一つです。
これをしっかり整備していなければロイヤルティや離職率などに大きな影響を及ぼします。
さらに、それが問題になった場合は自分が組織の責任者として取りまとめないといけなくなるため、特に精神面でかなりの負担を強いられることになります。
評価管理で思うこと
評価管理の業務では、
と感じます。
こちらも以下が楽しく思うポイントとつらいと思うポイントです。
| 楽しいポイント | つらいポイント |
|---|---|
| 評価制度を基に自分で人材育成や指示出しができること。 メンバーの業務のカイゼンやコミュニケーションがとりやすくなること。 | 評価制度が各要素と合っていないものがあると正当性がなくなり、特に部下やメンバーと関わる業務や関係に大きな支障が出ること。 |
楽しいポイント
まず、評価制度を通じて部下やメンバーとコミュニケーションを測り、それに合わせて自分で教育や研修ができることは楽しいです。
評価制度を基にメンバーの業務をカイゼンできれば、組織全体の成果や生産性があがる話になり、また人材強化にもつながっていきます。
もちろん、その人や自分にとっても、組織に対する貢献度が上がり、また成功体験を得ることができる話にもなります。
これを踏まえて組織内や自分と部下、メンバーなどとの関係性がよくなって業務が快適になります。
さらに、こういったことを通じてメンバーのポテンシャルにも気づくことができるため、そういった発見ができることも楽しく感じます。



ちなみに、行動経済学的にこういった問題を部下やメンバーと一緒に解決することは組織内における人間関係の構築にかなり友好的ですが、詳細は別記事で説明していきます。
この時、前提として評価制度がしっかり組織のコンセプトや理念、成果目標などとしっかり合っていて正当性があることがかなり重要です。
つらいポイント
逆を言えば、評価制度が他の要素と合っていないことから正当性が欠けていると、他の業務に支障が出て矛盾した状態に陥ります。
特に、部下とメンバーと関わる業務である組織運営や人材管理、動機付けなどや自分との関係性に大きな影響をもたらします。
部下やメンバーからすれば正当に評価してくれないと感じることから不満が募り、結果として自分に対する信頼や信用を失っていくことになります。



自分で評価制度を作ったわけではないのにそれを基にメンバーを評価しないといけない…という状態もあります。
それでカイゼンをしようとしても上層部に話が通らない…となったら負の部分だけ自分に来ることになるため、かなり精神的にきつく感じます。
動機づけで思うこと
正直、ここはチームマネジメントのやり方や人によって変わってくるところではあり、また現代ではシビアな部分になっています。



下手をするとハラスメントや労働法違反にあたってしまうため、この部分で頭を悩ませているマネジメント層も多いのではないでしょうか?
自分としては、
と思っています。
楽しく思うポイントとつらいポイントで分けると以下のようになります。
| 楽しいポイント | つらいポイント |
|---|---|
| メンバーのモチベーション向上によるパフォーマンス上昇が見込めること。 関係性の構築とコミュニケーションがしやすくなること。 感情や気持ちを共有できることから、人間性や社交性を向上させることができること。 | 組織のコンセプトや理念、価値観が部下やメンバーに浸透していないと、そのズレを刺激して逆に悪影響になる。 メンバーの心理的状況によってパフォーマンスが変わるため、その調整が難しい。 部下やメンバーとの適切な心的距離を取ることが難しい。 |
楽しいポイント
部下への心理的アプローチによる動機付けによって、部下やメンバーとのコミュニケーションと良好な関係の構築を促進できることは楽しいです。
このことで感情や気持ちといった心理的状況の共有や、それに伴う自身の人間性や社交性の向上を測ることができます。
ハーバード大学医学大学院・精神医学教授 ロバート・ウォールディンガー氏が主導した約85年に渡る成人発達研究では、人の幸福度に関して以下の結果が言及されています。
健康で幸福な人生を送るための唯一無二のベストな選択は、
『グッド・ライフ』ー幸せになるのに、遅すぎることはない
友好的な人間関係を育むことだ
つまり、動機付けによってよりよい人間関係を構築していくことは、自身だけでなく、部下やメンバーの幸福度を上げることつながります。
そして、こういった側面は結果として組織の生産性や効率を向上させる効果をもたらします。



これは、あるものがその市場を介さずによい影響を与えることを指す正の外部性と言われる効果です。
つらいポイント
しかし、この動機付けも自分と部下やメンバーの関係性や考え方、価値観などの条件がある程度そろった状態でなければうまく機能しません。
条件がそろっていない状態や誤ったやり方で行ってしまうと、人間関係または組織内における自身の立場の悪化をもたらす場合があります。
そういったことで組織内で肩身の狭い思いをすると、自身の存在意義を感じなくなったり気まずい思いをします。
さらに、モチベーションの刺激によるパフォーマンスの向上は良い方向に動くこともあれば、悪い方向に動くこともあります。
悪い方向になった場合、組織戦略の軌道や部下やメンバーとの関係性の修正はかなりシビアなものになる場合があります。



ここがよくマネジメント層が頭を悩ませるポイントです。
ハラスメントにならないか、その人の気に触れないか…などかなり気にするポイントとなります。
その他の業務で思うこと
最後に、マネジメント業務の一環で組織の生産性や問題をカイケツするために新企画の立案や自信の知識とスキルの向上を行っています。
ここでは、
と感じます。
この要素を楽しいポイントとつらいポイントで分けると以下に分解できます。
| 楽しいポイント | つらいポイント |
|---|---|
| 自己成長を感じられること。 変化をもたらせること。 | アウトプットができないと、やる意味を感じられないこと。 ちゃんとやると業務として重いこと。 |
楽しいポイント
この業務では、インプットからアウトプットができることから圧倒的に自分の自己成長を強く感じることができることが楽しいです。
限度はありますが、自身で挑戦して多少失敗しても自身で修正することができ、またそれをカバーできる組織としての環境が整っています。
そういったことを通じて自分だけでなく、組織にもよりよい変化をもたらして成果をあげることは、かなり大きな達成感を感じることができます。
つらいポイント
逆に、インプットは自分次第でできますが、アウトプットができないとやる意味を感じられなくなることがつらく思います。
アウトプットができない要因として、上層マネジメント層に自身の企画が正当に通らない場合があります。
このようなときは、特に将来性の観点からやる意味や必要性を感じなくなってしまいます。
あるいは、この業務は基本的に将来といった不確定要素が多いことや自身や組織にとって未知の部分のため、業務として重くなる場合があります。



特にはじめのことは一人で乗り越えないといけない部分があるため、その時はつらく感じます。
まとめ
たしかにマネジメント業務ではつらい部分はありますが、正直なところ、
で楽しくなります。
この記事を読んでいる方には下記のような方々など様々な方がいるかと思います。
仕事で自分の能力を発揮させてキャリアアップしたい方
実際にマネジメントをやっていてつらいと感じている方
これからキャリアアップを目指して就職活動をする方



新卒の方は最初の会社選びはかなり肝心です。
そして、キャリアアップを目指している方やマネジメントをやっている方は自身のスキルアップは大切です。
一方、今の職場ではキャリアアップが臨めないと感じている方や実際にマネジメントをやってつらい思いをしている方は、転職を視野に入れるのも選択の一つです。
今の時代では転職もしやすくなり、また転職した方が年収もキャリア、ライフワークバランスもよくなったというケースもあります。
そのため、場合によって、無理に今の職場の環境に適応する必要はありません。



そんな方は一度、転職、またはエージェントに相談されてみてはいかがでしょうか?
\ 特に20代の方にオススメ転職支援サービス! /