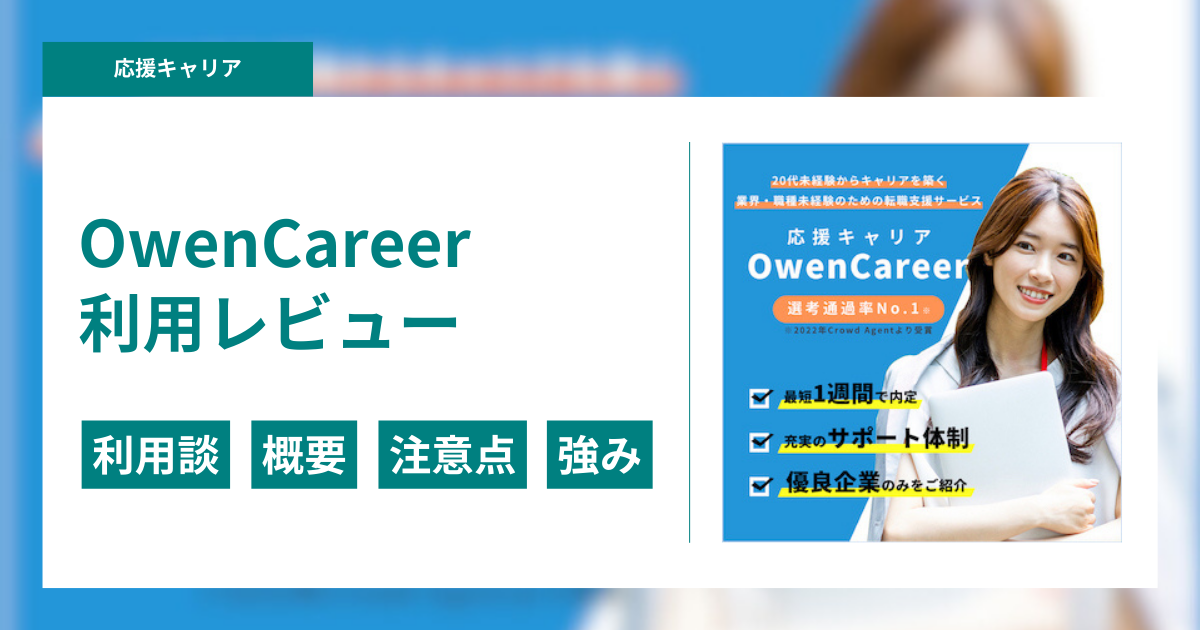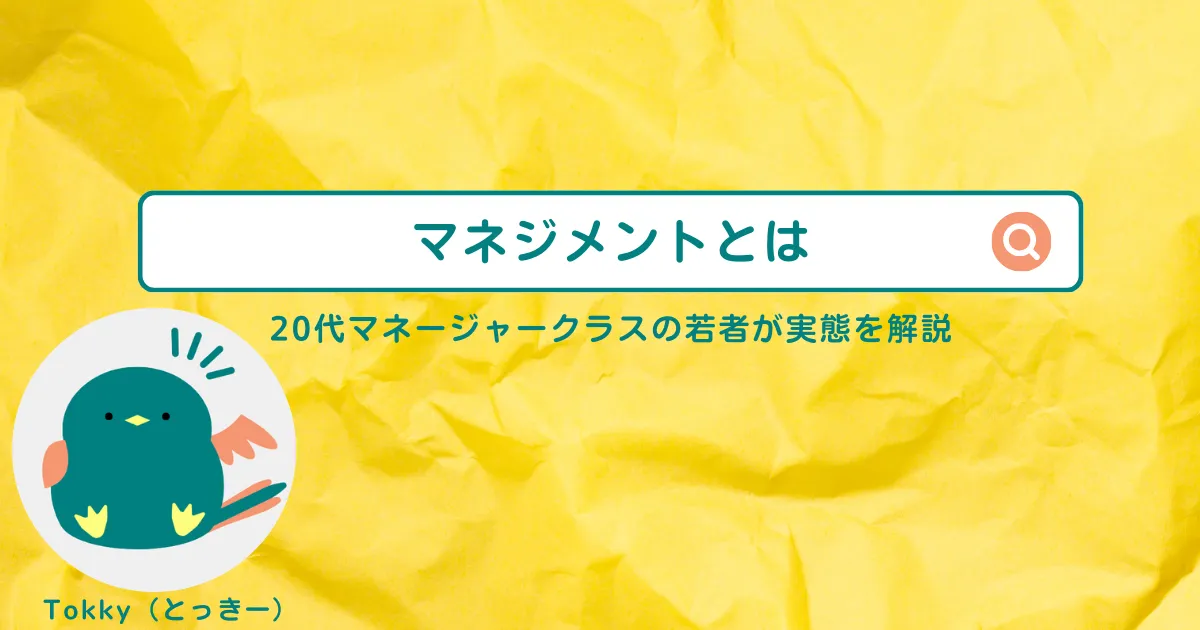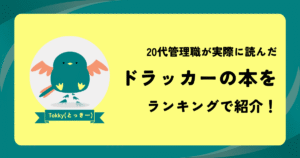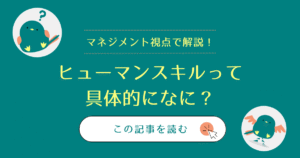この記事でわかること
- テクニカルスキルの概要
- 求められる人物像
- テクニカルスキル向上のメリット/デメリット
- テクニカルスキルの習得・育成方法
- テクニカルスキルを高めるポイント
そう聞かれた場合、あるいはそう疑問に思った場合、技術力や専門的な能力のことであると大体の人は想像するかと思います。
 Tokky(とっきー)
Tokky(とっきー)しかし、「具体的になに?」と聞かれると、意外と明確な言葉や定義で説明するのが難しかったりしませんか?
そのような背景がある中で、テクニカルスキルは、転職やキャリアアップにおいて重要なアピールポイントとなります。
面接官や採用担当者にとって、「この人は何ができるのか?」ということは非常に大切なポイントです。
そこで、今回は、
ということを、マネジメントだけでなく、転職やキャリアアップも視野に入れてお話ししていきます。



そして、この記事ではTokkyの知見を基に転職やキャリアアップを考慮したテクニカルスキルの習得・育成方法とそのポイントについてもお話ししています。
ここでしか読めないため、ぜひ最後まで読んでみてください!
テクニカルスキルの概要



まず、テクニカルスキルについて、主にマネジメントを軸にした観点から解説していきます。
テクニカルスキルとは
テクニカルスキルとは、特定の業務に関連する知識や技術、手法などを駆使して実務を遂行する能力のことです。
引用:https://teal-path.com/management/2911/
1955年にロバート・L・カッツが提唱したカッツモデルにおいて、管理職に求められるスキルの一つとして挙げられました。
カッツモデルとは、役職に応じて管理職に求められる3つのスキルのバランスが変化することを示した理論です。



「もっと詳しく知りたい!」と思った方は以下の記事を参考にしてみてください!


ノンテクニカルスキルとは
一方、1999年、欧州共同航空当局(JAA)※が主導したNOTECHSプロジェクトを通じてノンテクニカルスキルという言葉が登場しました。
※欧州共同航空当局(JAA)は、2009年に欧州連合航空安全機関(EASA)に統合されました。



そして、これをきっかけに、ローナ・H・フリン教授らによって2003年に学術的な定義と枠組みが提示され、また2008年に理論が体系化されました。
ノンテクニカルスキルの概要
ノンテクニカルスキルとは、
「テクニカルスキルを補完し、また安全かつ効率的な業務遂行に貢献する認知的・社会的・個人的資源としてのスキル」
引用:『Safety at the Sharp End: A Guide to Non-Technical Skills:SAFETY AT THE SHARP END』 Rhona Flin, Paul O’Connor
のことです。



“ノン”が頭につくことから対比的なイメージを抱きやすいですが、実態は互いに補完し合っている関係なのです。
テクニカルスキルとの違い
テクニカルスキルは知識や技術といった外的側面、または業務遂行という行動そのものに関するスキルです。
これに対し、ノンテクニカルスキルは、主に判断力や意思決定力、対人関係など、内面的または対人的側面に関わるスキルです。
ポータブルスキルとは
他方、2012年、日本で厚生労働省によって公式にポータブルスキルという概念が提示されました。



欧州や英連邦諸国では1970年代~1980年代半ばに登場し、トランスファラブルスキルと呼ばれています。
ポータブルスキルの定義
「ポータブルスキル」とは、職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキルのことです。
引用:厚生労働省 ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)



この対概念としてアンポータブルスキルがありますが、体系的な整理がされていないため、一般的にはまだ広く使われておりません。
テクニカルスキルとの違い
端的に言えば、業種や職種が変わっても持ち運びができるか否かがテクニカルスキルとの違いになります。



しかし、そもそもとして、提唱された背景が異なることから定義における視点も異なっています。そのため、テクニカルスキルとポータブルスキルは本質的に異なるスキルとなっています。
各マネジメントスキルとの違い
他方で、「え、でもどれも実務になるから結局はテクニカルスキルなのでは?」と疑問を抱いた方もいるかと思います。



自分もそのような疑問を抱いたため、整理しました。そこから導き出した各スキルとテクニカルスキルの違いについてお話しします。
コンセプチュアルスキルとの違い
コンセプチュアルスキルは主に判断力や意思決定力などの思考力に関するスキルであるため、ノンテクニカルスキルの一つに含まれます。
ヒューマンスキルとの違い
ヒューマンスキルは対人関係に関するスキルであるため、コンセプチュアルスキルと同様にノンテクニカルスキルの一つとなります。



対人関係にも技術が求められる側面はありますが、現在の考えを基に自分で考えた結論としては、ノンテクニカルスキルに分類するのが妥当であると推察します。
求められる人材像
基本的にテクニカルスキルは階層や立場などに関係なく全員に求められますが、階層によってその割合は異なります。



さらに、時代の変化に伴って階層も変化しています。それも踏まえて、どういう人が求められるのかお話ししていきます。
カッツモデル
カッツモデルでは、ロワーマネジメントの立場に近い者ほどテクニカルスキルを求められる割合が大きくなっています。
カッツモデルでは、マネジメント階層を上から順に
- トップマネジメント
- ミドルマネジメント
- ロワーマネジメント
の3つに区分しています。



カッツモデルの詳細は以下の記事で解説しているため、気になる方は是非ご覧ください!


ドラッカーモデル
一方、ドラッカーモデルでは、ナレッジワーカーが最もテクニカルスキルを求められるとしています。
ドラッカーモデルでは、カッツモデルにドラッカーのマネジメント理論を足して、
- トップマネジメント
- ミドルマネジメント
- ロワーマネジメント
- ナレッジワーカー
の4つにマネジメント階層を区分しています。
ドラッカーによれば、
「知識労働者は、ほとんどが専門家である。」
引用:『プロフェッショナルの条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】
「知識労働者が誰かの部下ということはありえない。同僚である。見習いの段階をすぎれば、自らの仕事については上司より詳しくならなければならない。さもなければ無用の存在となる。まさに、組織の中の誰よりも詳しいことこそ、知識労働者の知識労働者たるゆえんである。」
引用:『明日を支配するもの』 P.F.ドラッカー 上田惇生[訳]
と述べています。



つまり、テクニカルスキルを求められる人物像とは、その特定の実務を専門として行っている者であるということです。
テクニカルスキルの種類と具体例
時代の変遷や社会的・経済的な変化を経て、現在、テクニカルスキルは以下の3種類に分類されています。



この3種類に関して、転職やキャリアアップを軸にお話ししていきます。
汎用スキル
汎用スキルとは、テクニカルスキルにおいて職種や業種を問わずさまざまな実務に共通して求められる基礎的な土台となるスキルのことです。
- PC操作のスキル
- タイピング
- Excel/Word/PowerPoint
- コミュニケーションスキル
- 論理的思考スキル
- 自己マネジメントスキル
- 一般的なマナー
- 礼儀作法
- 尊敬語/謙譲語/丁寧語



例を見てみると、「え、これってポータブルスキルとかノンテクニカルスキルのことじゃないの?」と思った方もいるかと思います。
(実際、自分は思いました。)
確かに、例えばコミュニケーションはポータブルスキルやノンテクニカルスキルに分類される能力です。
しかし、テクニカルスキルの概要で触れましたが、各スキルごとでみている視点や焦点が異なります。
そのため、表現は同じでも、各スキルごとでその中身や捉え方なども異なってきます。



よって、少しややこしく感じられるかもしれないですが、厳密に言えば、汎用スキルはポータブルスキルやノンテクニカルスキルのことではないということです。
キャリアアップ視点
この汎用スキルは、例えば、未経験の方が新しくその業界・職種に挑戦するという場合に重要になってきます。
つまり、プレイヤーからマネージャーや管理職などマネジメントする立場に昇進する場合でも、汎用スキルが必要になるというわけです。
転職視点
キャリアアップも踏まえて、
- 新しい業界や職種に転職する
- その分野の専門スキルをまだ持っていない
などの場合は、この汎用スキルがしっかり備わっていることをアピールすることが重要となります。
専門スキル
専門スキルとは、特定の業務を遂行するにあたってその業界または職種では標準的な知識や技術等のことです。



簡単に言えば、その業界または職種における一般的な業務をこなすために必要とされるスキルのことです。
市場や商品知識
- その業界における各企業のポジション
- セブンイレブン/ファミリーマート/ローソン
- トヨタ/日産/スズキ/三菱自動車
- 利用者層
- 年齢/性別/住まい/年収/家族構成
- 各商品/特定の商品の特徴
- X(旧:Twitter)/Instagram/TikTok
- Windows/Mac PC
専門知識・技術
- プログラミングコード/システム
- HTML/CSS/JavaScript/Python
- 機械/建築/モノづくり関連
- 経営/経済/心理/マーケティング
- 社会福祉/医療
- 介護士/看護師/医者
- 法律/会計/税金/金融
- 行政書士/弁護士/公認会計士/税理士/ファイナンシャルプランナー
機械やPC操作
- 自動車の運転
- トラック/バス/その他特殊車両
- ショートカットキー
- ExcelのVBA/ピボット/関数の活用
接客/ビジネスマナー
- 顧客対応
- 電話対応
- クレーム対応
- 対面/受付/来客対応
- 営業スキル
- ヒアリング力
- トーク力/交渉力
- 資料作成力
※これは一部の例です。



専門スキルに関して、キャリアアップ、転職の2つの視点からみていきましょう。
キャリアアップ視点
キャリアアップとして、まずその業界・職種の未経験者は例で挙げたような専門スキルを最低限度まで身に着けることが第一の目標となります。
専門スキルを既に持っている場合は、それを深めていくか、別の専門スキルを身に着けて幅を広げていくかの主に2択になってきます。
転職視点
転職におけるキャリア採用では即戦力であることが求められるため、専門スキルが最低限備わっている必要があります。



よって、書類や面接で例で挙げたようなスキルがしっかり備わっていることを実績ベースで表示することが大切です。
特化スキル
特化スキルとは、専門スキルの高度化および応用によってさらなる付加価値を生み出す独自性の高いスキルです。
- ある分野で新しい価値を創出する(0→1)スキル
- ある分野における既存の価値を極限まで高める(1→100)スキル
- 経験知・暗黙知を用いた高度な判断力や実行力
- データ分析を基に自分で独自にカイゼンする
- 機械では判別できない病気を見つけられる
- 将来的に浮かりそうな課題や問題を発見する
- 感性や美的直感に基づく他者には真似できない創作スキル
- 模倣が難しい自分だけの知識や技術
※これは一部の例です。
特化スキルにおける専門スキルの高度化および応用には、ノンテクニカルスキルの活用が不可欠となってきます。
なぜなら、ノンテクニカルスキルとうまく掛け合わせることによって単に実務をこなす専門スキルが特化スキルへと昇格するからです。



この特性から特化スキルは独自性が強まる傾向にあるため、ある意味「職人」に近いイメージとなります。
キャリアアップ視点
そのキャリアまたは分野を極めるためには、この特化スキルを身に着けることが必須となってきます。
転職視点
転職において、この特化スキルは大いに有利かつ最大のアピールポイントとなります。



しかし、後ほど説明しますが、特化しすぎている場合は逆効果になってしまう場合があるため、この点には注意が必要です。
3種類を基にしたテクニカルスキルの体系図
ここまで現代におけるテクニカルスキルの3種類についてお話してきましたが、これらをまとめると以下のようになります。


イメージがついている方もいるかと思いますが、汎用スキルを基に伸ばしていくと最終的には特化スキルになっていきます。



しかし、実際はノンテクニカルスキルなども絡んでくるため、全体で見ると実態は結構複雑になっています。
テクニカルスキル向上のメリット
前章で少し触れている部分もありますが、テクニカルスキルを伸ばすことによって次のようなメリットがあります。
生産性や効率性、成果などの向上
まず、マネジメント視点でいえば、テクニカルスキルの向上は生産性および効率性、成果の向上などをもたらします。
組織メンバーのテクニカルスキルを伸ばすことによって、一人ひとりの専門性が高まり、またそれに伴って生産性や上がってくる成果物も大きくなります。
さらに、自身のマネジメントに関するテクニカルスキルを向上させることができれば、組織活動における生産性や効率性を上げることができます。



つまり、テクニカルスキルが向上すれば自分含めた一人ひとりのレベルが上がり、またそのことで様々なものも向上するというわけです。
キャリアアップが臨みやすくなる
キャリアアップを目指す上で、テクニカルスキルの向上は避けて通れません。
なぜなら、その分野を極めていく場合、専門スキルを特化スキルまで向上させる必要があるためです。



その業界・職種が未経験の方は、まず最低限度の専門スキルを身に着けなければ、そもそもその分野のキャリアアップが臨めません。
プレイヤーから管理職になる場合でも、職種が変わることから初めは汎用スキルが求められます。



よって、キャリアアップをしたいという場合は、3種類のテクニカルスキルの向上が欠かせないということになるのです。
転職で優位になりやすくなる
テクニカルスキルを向上させることによって、転職で優位に立ちまわることができるようになります。



もちろん、伸ばすことや持っていることが大切ですが、転職ではそれらを面接官にうまく伝えて理解してもらうことが重要です。
このことを前提に、テクニカルスキルの3種類を基に細かく分けてさらにお話ししていきます。
汎用スキルを向上させた場合
未経験の業界や職種に挑戦しやすくなり、結果としてキャリアチェンジやキャリアの選択肢の拡大をしていくことが可能となります。
加えて、未経験の方が多い業界や職種では、ポテンシャルの高さを表すことに伴う自身の希少性を表すことも可能となります。
専門スキルを向上させた場合
専門スキルを持っていれば、転職時に即戦力として活躍できることをアピールしやすくなります。
さらに、専門スキルを向上させていけば特化スキルになっていくため、キャリアアップだけでなく、上のクラスの転職も可能になります。
特化スキルを向上させた場合
特化スキルまで持っていれば、労働市場における希少性の高さによって企業から高い評価を得ることができます。
さらに、この特化スキルを向上させていけば自分だけのスキルになっていきます。



そのため、その属人性をうまく利用すれば給与や待遇に関する交渉も優位に立ちまわることが可能となります。
テクニカルスキル向上のデメリット
先ほどはテクニカルスキル向上によるメリットについてお話ししましたが、デメリットも存在します。
教育/習得にコストがかかる
まず、テクニカルスキルの向上において、教育・習得コストがかかってしまうことがデメリットとして挙げられます。
特に、特化スキルまでの教育および習得において、時間や費用、労力などのコストがとてもかかってきます。
なぜなら、ただ単に専門スキルを伸ばすだけでなく、ノンテクニカルスキルの向上も必要になってくるためです。



よって、マネジメントでは教育・習得に関して可能な限り生産性および効率性を上げておくことが大切です。
転職では、専門スキルがあれば教育コストがかからないことを踏まえてアピールすると好印象になりやすいです。
他スキルとの教育/習得バランスが難しい
一方で、他スキルとの教育/習得バランスを保つことが難しいことも課題としてあります。
例えば、専門スキルにおいても細かく見ていくと、
- 業界/専門用語
- 特定のツールの使い方
- 手技/身体技能
など、様々な要素があります。
そして、コストの面でも触れた特化スキルの教育や習得だけでなく、実際でもヒューマンスキルやコンセプチュアルスキルおよびそれらの向上が必要です。



よって、何を優先して習得していくか、あるいは教育をしていくかなどの優先順位と割合を決めて管理することが重要です。
特化スキルによる汎用性の低下と属人化
加えて、他スキルとの教育/習得バランスを保てずに特定の分野のみを極めていってしまうと、汎用性が低下してしまうという場合が出てきます。
なぜなら、その分野や特定の場面では突出していても他の分野になった途端に価値がなくなるといった活かせる場面や分野が限定的になるためです。
さらに、環境やトレンドの変化によってそのスキルの需要が下がると、自分のその強みがなくなってしまうというリスクも発生します。
他方で、属人化してしまうというデメリットが発生する場合もあります。
確かに、特化スキルをに伸ばすことによって、自分にしかできないという希少性を基に自分の価値を高めることができます。
しかし、それは逆に自分にしかできないというリスクを発生させることになります。



よって、マネジメントでは属人化を避けるために教育プロセスを体系化し、その環境や体制を整備しておくことが重要です。
転職では、面接官がこのような内容で捉えないようにうまく特化スキルをアピールする必要があります。
テクニカルスキルの習得・育成方法
テクニカルスキルの習得・育成に関して、一般的には様々な方法が挙げられています。



結論、それらは正しいですが、ここではそれを踏まえた個人的見解も含めたテクニカルスキルの習得・育成方法についてお話しします。
実践で経験を積む方法



正直、個人的に「百聞は一見に如かず」という考えを持っているため、手っ取り早くテクニカルスキルを習得・育成する方法は実践を積むことだと思っています。
正確には、実践を通したインプットとアウトプットをPDCAサイクルに落とし込む方法が、個人的に思う効果的な方法です。
インプットとアウトプット
実践の前にある程度のインプットは大切ですが、時にはいきなり実践してみるということも大切です。



映画『アイアンマン1』でも、トニー・スタークが1番初めに開発したスーツを試すときに「時には歩く前に走ることが必要なんだ」と言っていました。
PDCAサイクル
ただし、ここで重要なのはただ実践を積むだけでなく、そこから「次はどこをカイゼンすればいいのか?」といったPDCAサイクルにしてそれを回していくことです。
※PDCAサイクルとは
仮設思考に基づいて「Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Action(改善)」を繰り返すことによって効率的かつ効果的に業務を進める施行のことです。人によって、Action(改善)をAdjust(調整)とすることもあります。
※仮説思考とは
目標を達成するために仮説を指す仮の結論を立て、それに基づいて情報収集や検証、修正を行うロジカルシンキングの一つを指します。



実際、トニー・スタークも実践を通じて様々な改良を施していましたよね。そんなイメージです。
業務内容の整理
そして、習得・育成する上で業務内容を整理していくことも効果的かつ効率的な方法です。
ドラッカーも、
「仕事を理解するうえでまず必要とされることは、他のあらゆる客観的な事象を理解するための第一歩と同様、分析である。仕事の分析とは、基本的な作業を明らかにし、論理的な順序を並べることである。」
引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】
と述べています。
実際、業務内容を整理することによって、具体的に何の知識や技術を習得・育成すればいいのか分かりやすくなります。



加えて、マネジメントでは、業務内容の整理は評価軸や評価制度の整備にもつながっていきます。
習得/教育体制および環境の整備
さらに、業務内容の整理に伴う習得/教育体制および環境の整備を行うことも特にマネジメント観点では効果的かつ効率的です。
ここで、生産性はもちろん、フィードバックと継続学習の要素または仕組みを意識することが重要になってきます。
なぜなら、ドラッカーによれば、生産性も合わせたこの2つによって、働きがいなどの動機付けができるからです。



下記の記事で触れていますが、個人的に、人材マネジメントにおいて教育がすべてと思っているくらい大切にしています。


テクニカルスキルを高めるポイント



育成・習得方法に加えて、個人的に思うテクニカルスキルを高めるポイントは以下になります。
資格を取得/保有すること
その分野のおいて資格が存在している場合は資格を取得して持っておくとよいです。
実際に資格がなければできない業務や職種があるため、資格があれば実践でできる範囲および経験を増やすことができます。
加えて、特別な資格を持っていれば転職やキャリアアップ、さらには年収の面で大いに有利になれます。



ちなみに、自分は仕事の関係で「貸金業務取扱主任者」という金融の資格を取得しています。
会社をしっかりみること
そして、テクニカルスキルを高めるうえでは、会社の環境はとても重要になってきます。
例えば、「様々なことに挑戦したい!」という場合は、中小規模やベンチャー企業に転職した方がオススメです。
なぜなら、人手不足から別の分野の仕事を任されることや、融通の利きやすさから自分の要望が通りやすいことなどがあるためです。
一方で、「安定的にその分野のキャリアを歩みたい」という場合は、大手企業の方がオススメです。
なぜなら、中小やベンチャー企業とは対照的に大手の方が業務が多岐に渡ることが少なく、基本一つの分野に集中できるためです。



つまり、目的や展望によっては給与・待遇面だけでなく、会社の規模や環境なども肝心になるというわけです。
ノンテクニカルスキルも向上・育成する
特化スキルに関するお話でも触れましたが、テクニカルスキルを高めるために、ノンテクニカルスキルの向上・育成も行うとよいです。
ノンテクニカルスキルはテクニカルスキルを補完するスキルでもあるため、関係的にテクニカルスキルを高めるためにはノンテクニカルスキルも高める必要があります。
さらに、ノンテクニカルスキルおよびその向上は専門スキルを特化スキルにする際や、特化スキルを向上させる際にも必要になってきます。
まとめ|テクニカルスキルとはなにか?
これまでの話を踏まえて、テクニカルスキルは、その特定の実務を専門として行っている者に求められるスキルと言えます。
そして、テクニカルスキルは3種類から構成されており、またそれらをマネジメント視点で整理すると以下のようになります。
<3種類の比較表>
| 種類 | 学習コスト | 市場価値 | 代替可能性 |
|---|---|---|---|
| 汎用スキル | 低 | 低 | 高 |
| 専門スキル | 中 | 中 | 中 |
| 特化スキル | 高 | 高 | 低 |



上記の特性を基に、マネジメントではメンバーのテクニカルスキルの教育・育成を考えて実行していく必要があります。
他方、転職やキャリアアップでは、この3つの特性を軸に対策を練って実行していく必要があります。
そして、テクニカルスキルを高めるポイントでお話ししましたが、キャリアアップを目指した転職では給与や待遇だけでない会社の見方が大切になってきます。



そのためには、自分一人だけでなく、第三者の視点や手を借りながらやっていくことが効果的かつ効率的です。
ぜひ、キャリアアップのために転職を考えている方は下記から動いてみてください!
\ ハイクラスを目指すならここがオススメ /