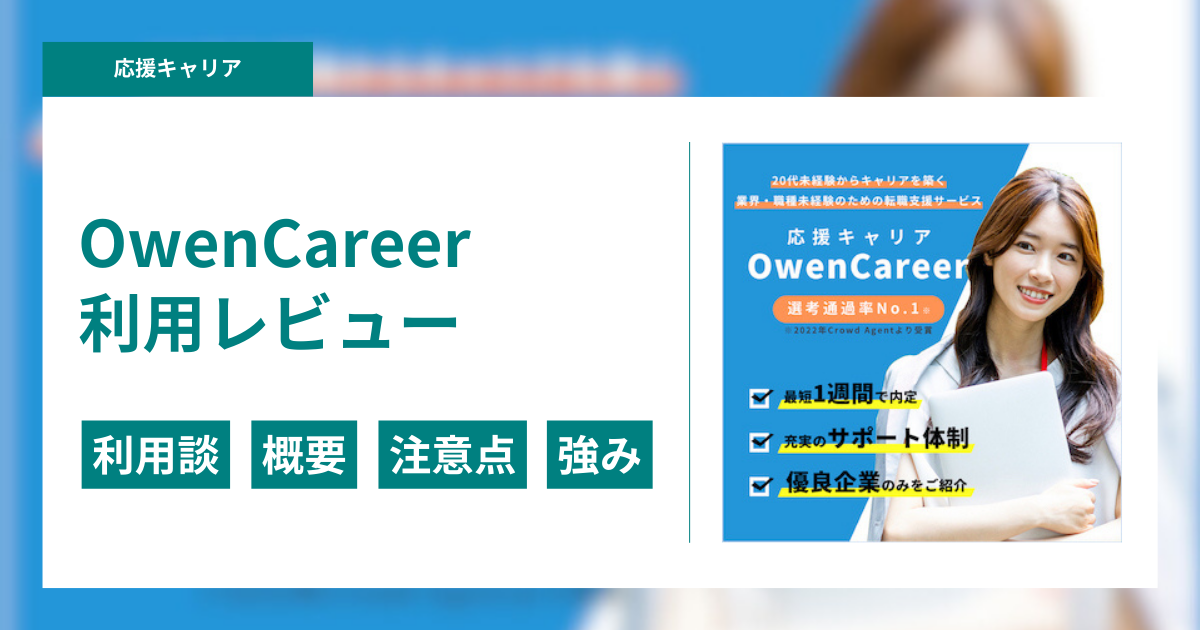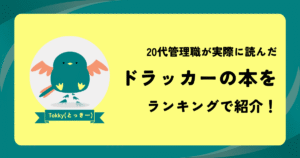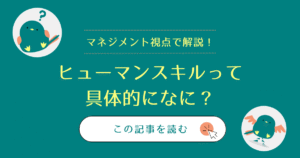この記事でわかること
- ロワーまたはミドルマネジメントの業務内容
- その業務内容は主に5つで構成されていること
- 各業務の軸は「人を動かす」こと
- 管理職を目指す上で自分が将来行うこと
キャリアについて、現代ではかなりワークライフバランスが重要視されるようになりました。
このことに伴って、就活や転職するときに大半の人が
- 勤務時間は?
- 休日は年間何日?
- 福利厚生は?
- プライベートの時間はどれだけ取れるの?
などを大きく気にするようになりました。
そんな中、将来やお金のことなどを考えてこう思っている人もいるでしょう。
 Tokky(とっきー)
Tokky(とっきー)自分もそう思っている人です。
今の会社にインターンから新卒で入れてもらい、実際、管理職になってマネジメントを任せてもらえるようになりました。
管理職になってマネジメントを行うことはキャリアアップにおける道の一つです。
しかし、キャリアアップで管理職を目指す際、
「マネジメントって具体的に何するの?」
って思いませんか?



こんなことを先に知っておくと自分のキャリア形成や具体的な目標が立てやすくなりますよね。
今回は自分が実際にこなしている業務からお話ししていきます。
マネジメントの業務内容



組織内でTokky(とっきー)は、ロワーマネジメントまたはミドルマネジメントを担当しています。
そのため、今回お話ししていく内容は、その階層における業務内容ということになります。
そもそもマネジメントとは?
しかし、ここで、「え、ロワーマネジメントってなに?」「ミドルマネジメントって?」と思う方もいるかと思います。



今回のお話はこちらの記事で書いてあるマネジメントの定義を基に話しているため、そんな方はぜひ読んでみてください!
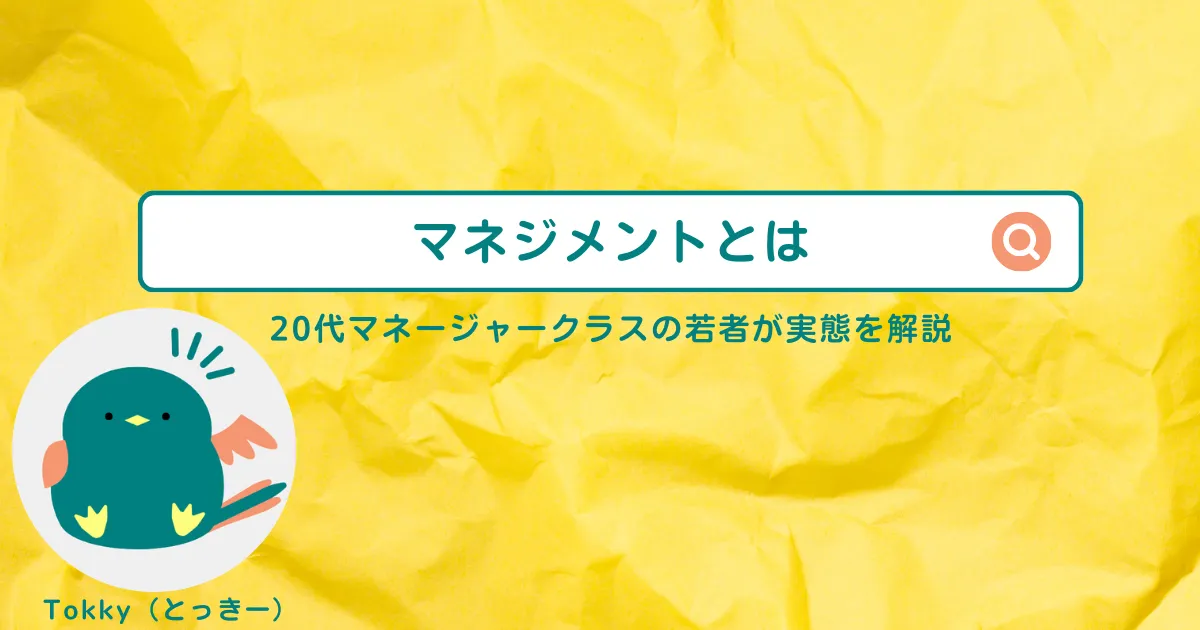
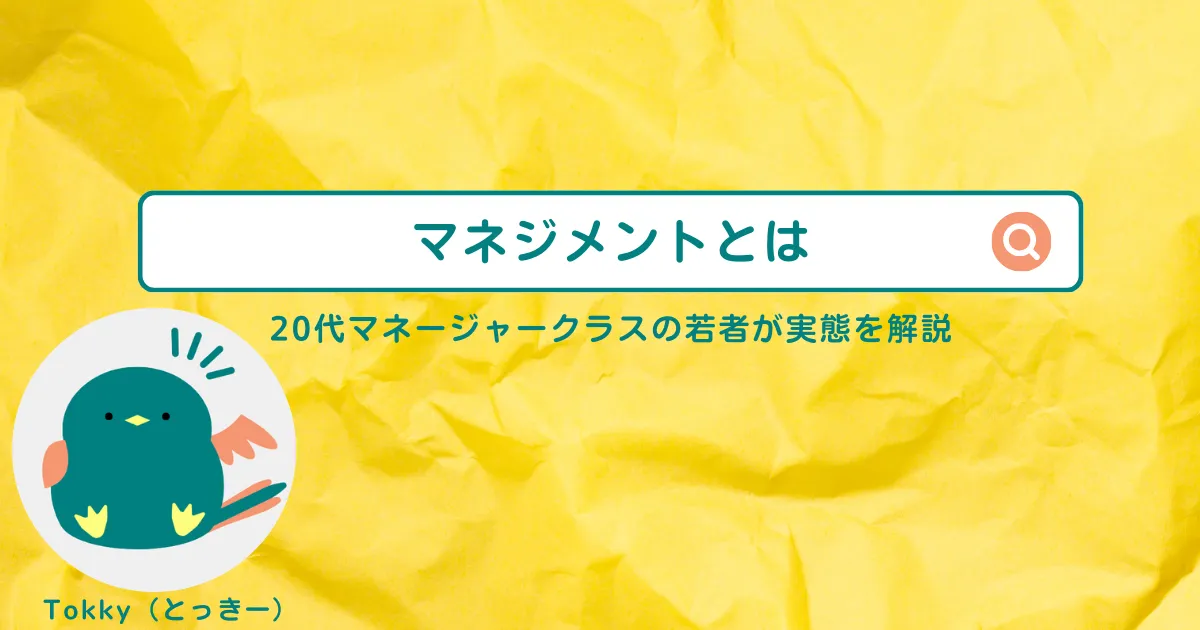
普段の業務内容一覧



上記の記事から来ていただいた方はありがとうございます!
ここからが本題になりますが、いつもマネジメントにおいては下記のような業務を行っています。
- 組織運営(チームマネジメント)
- 目標または指標の設定(予算・売上管理)
- 人材管理
- 評価管理
- 動機づけ



これを基に各マネジメント業務に関して細かく話していきます。
組織運営(チームマネジメント)
まず始めに、マネジメントの業務内容として、マネジメントを行う行為の意味そのもの指す組織運営があります。
特に自分が担っているマネジメント階層の組織運営の業務は、主にチームマネジメントのことを指します。
チームマネジメントとは、目標や指標の達成のためにチームを最適に運営または管理していくことです。
そして、マネジメントの定義からチームマネジメントでもそのチームにおける経営資源の有効活用をすることが求められます。



ここで、Tokky(とっきー)的には、チームマネジメントで一番重要なことは、「『人』、すなわち人的資本をどう上手く使っていくか」であると日々の業務から感じています。
つまり、チームマネジメントの実態とは、組織の目標および指標の達成のために「人を動かす」ということになります。
この内容に関して、さらに詳しく見ていきましょう。
チームビルディング
チームビルディングとは、そのチームの目標達成のために各メンバーとそのメンバーで構成されるチームの能力を最大限発揮できるようにチームを構築することです。
毎回行うわけではないですが、新規事業や新規企画の立ち上げ、新人採用など何か新しいことや資本を投下する場合に発生します。
チームビルディングは主に以下のステップで行っていきますが、設定や構築は上流マネジメント層が行い、実行のみを自身が担うなど様々な場合があります。
目標および指標の設定
次章で詳しくお話ししていきますが、まずチームで達成するための成果を定めていきます。
必要なタスクと経営資源の算出
そして、定めた目標および指標を達成するために、それらを因数分解して必要なタスクや経営資源を洗い出していきます。
理念とコンセプトの設定
タスクや経営資源を算出したら、このチームを運営するにあたってどのような
チームの全体像の把握と構築の実行
STEP1とSTEP3のマクロ的要素とSTEP2のミクロ的要素から成るチームの全体象を把握した上でその構築と実現を行っていきます。
チームマネジメント
チームビルディングも含めてチームマネジメントを通じて人を動かしていく際、具体的にやっている業務としては主に下記になります。
- オペレーション設計/管理
- マニュアル作成/管理
- 内部環境や設備の設定/管理
- 指示だし/コミュニケーションの促進
- シフト調整/管理
- チームにおける課題解決&活性化



他の業務にも関連づくため、ある意味組織運営はマネジメント業務の本幹と言える業務と言えます。
チームにおける課題解決&活性化
ここでチームにおける課題解決&活性化は、組織運営の中で以下のような課題やトラブルなどにぶつかったときに発生します。
- 「実際に始めてみたら想定と違った」
- 「もっと効率的かつ最適なやり方が見つかった」
- 「組織内または外の状況や環境が変わった」
- 「新たな条件や指標が課された
このような時にこれらの課題を解決し、またその発生源となった要素を修正してチームの最適化および活性化を行っていきます。
言い換えれば、目標および指標の達成に向けたチームの最適化を図るためにPDCAサイクルを行うことと言えます。
※PDCAサイクルとは
仮設思考に基づいて「Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Action(改善)」を繰り返すことによって効率的かつ効果的に業務を進める施行のことです。人によって、Action(改善)をAdjust(調整)とすることもあります。
※仮説思考とは
目標を達成するために仮説を指す仮の結論を立て、それに基づいて情報収集や検証、修正を行うロジカルシンキングの一つを指します。
目標または指標の設定(予算・売上管理)
チームマネジメントでもどのマネジメント業務でも当てはまりますが、PDCAサイクルを行うことも考慮して目標または指標を設定する必要があります。
そのために、先月末~当月頭にかけて先月の振り返りと当月のKGIとKSF、KPIの設定を行います。
KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)とは
組織やプロジェクトが最終的に達成すべき目標を表す指標のことです。
実際に自分が掲げているものも含めた例として、売上金額やCV数などがあります。
KSF(Key Success Factor:主要成功要因)とは
事業が成功するために必要な条件のことです。
例えば、実際に自分で立てたことがあるものとしては、「(○○を行った)顧客に対して早くアプローチをかける」などがあります。
KPI(Key PerformanceIndicator:重要業績評価指標)
KGIを達成するためにプロセスの達成度を示す中間目標の指標、またはKGIの中間目標ともなる数値で設定したマーケティング目標のことです。
自分が定めた例としては、案内人数などがあります。



ちなみにTokky(とっきー)は組織図の関係上2チーム分行っているため、先月末~当月頭にかけては結構忙しいことが多いです。
加えて、業界や事業モデル上、ほぼほぼ予算や売上管理と等しくなります。
そして、以下の3つの振り返りを通じて当月の目標の設定を行っていきます。
- KGIおよびKPIの達成度と展望
- 定めた指標の各相関度および妥当性
- 行った施策の分析
これらについて、詳しくお話ししていきます。
KGIおよびKPIの達成度と展望
まず、自分が定めた目標に対して実数はどのくらいの割合だったかをそれぞれ算出していきます。
例えば、「売上1,000万円というKGIに対して実数は1,100万円だった」という場合の達成度は「110%」と表します。
そこから、達成度が高い指標は「なぜよかったのか?」、逆に低い指標は「どこをカイゼンすればいいのか?」ということを分析していきます。
さらに、「指標の数字は上げられるのか?」「指標の数字を上げるために必要な要素は何か?」という展望や将来性も模索していきます。
定めた指標の各相関度および妥当性
定めた指標であるKGIとKPIが正の相関関係になっているか、またはその因果関係の正しさや強さなど2つの関係の妥当性を測っていきます。
性質上、KPIはKGIを因数分解した指標であることからKPIを四則演算した解がKGIとなり、またこのことからKGIとKPIは互いに導き出せる関係と言えます。
これより、どちらの目標も達成または未達成となっていようが、相互関係がなければその指標自体に意味や価値はないのです。
よって、達成しているかしていないのかという確認だけでなく、しっかり指標そのものの妥当性も確認していきます。
行った施策の分析
指標の達成度と関係性の確認とも関連しますが、目標達成のために行った施策、すなわちKSFの適切性や課題点も確認しています。
計算上で合っているのかという確認だけでなく、内部環境と外部環境を整理して経営戦略として妥当なのかということも確認していきます。
なぜなら、例えば、直近では某小売会社は、業績を上げようとして食品パッケージや食品そのものを加工した戦略を取りました。
しかし、結果として業績は上がらずに、むしろ消費者の心象やブランドイメージを下げることになってしまいました。



この例では業績というKGIも達成されておりませんが、指標といった理論上の計算式だけでは見えない部分があるのです。
このような振り返りを基に当月の目標を立てていくという繰り返しを行っていきます。
人材管理
冒頭でも言いましたが、チームマネジメントは人を動かすことでもあるため、そもそも「人」がいなければ成り立ちません。
つまり、チームマネジメントの業務の大半はチームの目標および指標の達成のために人を管理する人材管理を行うことと言えます。
人材管理における主な業務内容としては、以下の3つになります。
- 必要人的資本の担保
- 人材採用
- 部下の教育
必要人的資本の担保
この業務は動機付けの一部とも言えますが、チームの目標および指標の達成のために必要な人的資本を維持していく必要があります。
その方法として新しい人を採用していく方法もありますが、自分についてきている部下の管理も重要になります。
新しい部下の研修や教育が終わったからといって、それ以降は特に何もしなくていいとはなりません。
もとを言えば基本的に部下の教育に終わりはないのですが、既存の部下との関係の維持または向上を測らなければなりません。
人材採用
ここでいう人材採用とは、社内または社外から自身の組織に人的資本を追加することを指します。
具体的に言うと、社外からの人材採用というのはいわゆる求人募集を指し、社内は部署や所属組織の異動などを主に指します。
この業務は、会社組織の実態や自身の社内的立場や裁量権、マネジメントの階層などによって大きく変わってきます。
例えば、個人オーナーや中小企業、トップマネジメント層などであれば人材採用に関して多少の融通を利かせることができます。
一方、大手企業や採用は人事部が担当するなどの場合は、自身の人材採用の裁量に関して多少制限がかかってきます。



ちなみに、Tokky(とっきー)は求人媒体の選定から採用、研修まで一人で一貫して行っています。
部下の教育
人材採用や新しいことをしていくとなった場合、必然的に発生するものが自身の部下となるそのメンバーへの研修・教育です。
ここで、新人教育において教える側と教わる側の双方にとって研修カリキュラムが肝となってきます。
教える側としては研修進捗の把握や研修のマニュアル化のためというのもありますが、進捗管理として重要なものとなります。



教わる側としても自身が行う業務内容の把握などで重要な役割を果たしますが、どちらかといえば今後何をやっていくのかという目安が分かる安心感を得るという方が適切かもしれません。
いずれにせよ、研修カリキュラムは教育において重要となるため、ない場合は作成をしていく必要があります。
ある場合はもちろんそれを使っていきますが、しっかり中身を見直して必要があればカイゼンをしていきます。
評価管理
あらゆる面でも言えますが、チームマネジメントや目標設定、動機づけ、人材管理などにおいて評価制度はかなり重要な役割を担います。
例えば、人を動かすことにおいて、評価制度を設ければ部下にとってそれが動く動機、アンカーとなります。
なぜなら、部下はその評価を得たい、満たしたい、または満たさないといけないためです。



もちろん、評価制度の設計や指示出しの仕方などによって感じ方に差異は出てきますが、少なからず部下の動機の一つとなります。
他方で、教育や研修も含めた人材管理において、評価基準はそれらの目標や指標になってきます。
このようなことから、チームマネジメントや人材管理を行っていく上で評価制度の管理も行う必要があるのです。
評価制度の管理として行う業務は主に以下の3つとなります。
- 評価基準または評価制度の作成
- 評価基準の進捗確認
- 評価制度のカイゼン
評価基準または評価制度の作成
まず評価基準がない場合、組織図や全体の目標設定から逆算して評価基準や制度を設定していく必要があります。
この時、この評価基準の設定はかなり難しいですが、売上や件数といった数字だけでなく、態度や姿勢、その他数字だけでは表せない指標も含めた方が好ましいです。
なぜなら、目標設定の章で話したように数字だけでは見えない、または表すことが難しい要素があるためです。
例えば、その人がいると安心感がある、周りのメンバーの評価基準などに対してよい影響を与えているなどが該当します。
これを考慮しないと各メンバーの評価はいいのにチーム全体の生産性は悪いなどのバイアスが発生することがあります。



ちなみにこのバイアスは経済用語で合成の誤謬と言われており、日本の少子高齢化の要因として一部からこのバイアスが指摘されています。
評価基準の進捗確認
評価基準を設定、または元からある場合はそれに従って部下または組織全体の目標に対する進捗を確認します。
理論上は部下たちの評価基準を加算したものがKPIまたはKGIの指標の値と等しくなるため、その評価基準を達成できるように部下に指示を出して動かしていきます。
これも評価制度の設計によりますが、進捗がよくない場合はオペレーション内容や環境設定などをカイゼンして指示出しを行います。
ここで、進捗がよい場合でも何もしないというわけでなく、その要因やもっとよくなる方法などを模索してくことも大切です。
評価制度のカイゼン
目標指標や内部環境、外部環境などの変化に伴い、評価制度や基準も見直してカイゼンしていく必要があります。
こちらも他の業務と同様にチームの最適化や活性化のために日々PDCAサイクルを回していくことになります。
動機づけ
特に人を動かすというチームマネジメントや人材管理において、部下たちの心理も考慮していかなければなりません。
心理的要素によって人は限定合理性を持ち備えているため、組織やチームにもこの性質は影響していきます。
限定合理性とは
さまざまな制約条件によって、人または人の行動・選択は限定された合理性しか持ち得ないことを指す経済用語のことです。
よって、マネジメントにおいてこの心理的アプローチを通じた部下の動機づけというのも場面において発生します。



この動機づけに対する考え方ややり方として、「人情型」と「非情型」の2つに大きく分かれるとTokky(とっきー)的には考えています。
人情型で動機付けを行う場合は、部下との面談やコミュニケーションなど人間関係の向上によって動機付けしていく流れとなります。
そのことでモチベーションや気持ちを上げて人を動かして成果を生んでいきますが、限定合理性の影響を強く受けるため、効率性が欠けてしまう可能性があります。
一方で、この対局にあたる非情型の場合は、組織から人単位が行う業務の効率性や生産性の向上を重視します。
そのため、厳密には全くしないというわけではありませんが、部下に対する動機づけはほぼ行いません。
よって、成果目標の達成においては合理的かつ効率的ですが、人間関係の希薄化や組織に対するロイヤリティが低くなりやすいのが欠点として挙げられます。



場面やメンバーの属性によりますが、個人的にはどちらかというとこの非情型タイプが軸の人ですね。
その他
ここまで、主に5つのマネジメント業務内容についてお話ししてきましたが、実はそれ以外でも付随して行っていることがあります。



これも会社という組織などの場合によって様々ですが、主に以下の2つの業務を行っています。
- 新企画の立ち上げ~付加価値の創出
- 知識・スキルの獲得



特に「もっとキャリアアップしたい!」という人などにとっては、行った方がいい内容です。
では、実際の内容について話していきます。
新企画の立ち上げ~付加価値の創出
普段のマネジメント業務と並行して、現場の課題をヒントに新企画をミドル、またはトップマネジメント層に提出して実際に行う時があります。
もちろん、トップマネジメント層が新たな経営戦略や事業・サービスのカイゼン案を出して実施していく場合もあります。
トップマネジメント層が決めた案を形にするために、現場設計〜運用まで行って新たな付加価値を生み出さなければなりません。



正直、最初はかなりつらいですが、自然と組織に組み込んでいって適切な形にすることを目指していきます。
知識・スキルの獲得
加えて、各マネジメント業務や付加価値の創出に付随していきますが、常に新しい知識やスキルを得ていかなければなりません。
日々自身の知識やスキルを更新していって部下におろしていき、組織における人的資本の強化に努めていきます。
そうすることによって、組織の課題のカイゼンにつながり、また最終的に目標および指標の達成に向けた組織の活性化にもつながっていきます。
まとめ



今回は、Tokky(とっきー)が普段行っていることからロワーマネジメントまたはミドルマネジメントが行っている具体的な業務内容について解説してきました。
- 組織運営(チームマネジメント):目標や指標の達成のためにチームメンバーを動かし、それを最適に運営または管理していく業務
- チームビルディング
- チームマネジメント
- チームにおける課題解決&活性化
- 目標または指標の設定:先月末~当月頭にかけて先月の振り返りと当月のKGIとKSF、KPIの設定を行う業務
- KGIおよびKPIの達成度と展望
- 定めた指標の各相関度および妥当性
- 行った施策の分析
- 人材管理:チームマネジメントの大半を占める業務であり、主に「人」の管理していく業務
- 必要人的資本の担保
- 人材採用
- 新人教育
- 評価管理:チームマネジメントや人材管理を行っていく上の目標や指標、または部下の動機づけに用いるための評価を管理する業務
- 評価基準または評価制度の作成
- 評価基準の進捗確認
- 評価制度のカイゼン
- 動機づけ:人を動かすというチームマネジメントや人材管理において、部下やチームメンバーに対して心理的アプローチを行う業務
- その他:組織の最適化や活性化のために、新企画の立ち上げ~付加価値の創出や、それに伴う新しい知識やスキルなどを獲得していく業務
先にマネジメントの業務内容を知っておくと、自身の将来のキャリア設計が組みやすくなります。



しかし、もっとさらに細かく知っておくとイメージが湧くのではないでしょうか?
そんな方は以下の記事を参考に続けてみてください。