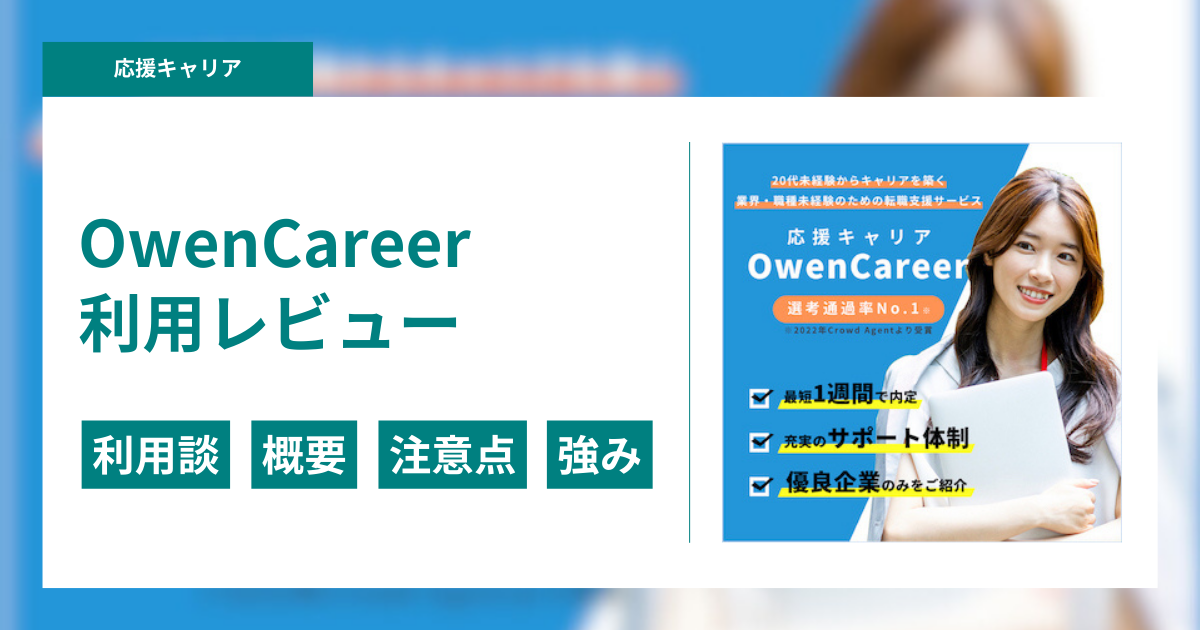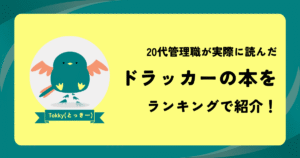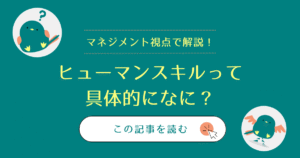この記事でわかること
- マネジメントスキルの概要
- 実務で求められるマネジメントスキルの内訳
- Tokkyの実体験からのオススメアドバイス
- マネジメントスキルの効果的な身に着け方
- マネジメントスキルの効果的な伸ばし方
 Tokky(とっきー)
Tokky(とっきー)記事をご覧のみなさん、こんにちは!
20代で事業とコールセンターの組織をマネジメントしているTokky(とっきー)です!
少し突然ですが、例えば、
- 将来管理職になってマネジメントをやっていきたい!
- 昇進して部下を持つようになった…
- 会社でマネジメントを任された…
などでマネジメントについて学びたい、もしくは学ばないといけないって時がありますよね。
そうやって様々なことを学んでいくと思いますが、
って思う時がありませんか?
今回はそんな方に向けて、実際に自分が普段行っている業務を基に
についてお話ししていきます。



さらに、そこから実体験を基に身に着け方と伸ばし方についてもお話しします!
マネジメントスキルの概要
まず、自分が実務を通じて思うマネジメントスキルについてお話ししていきます。
マネジメントスキルとは
マネジメントスキルとは、組織やチームの目的または目標を達成するために、 人・モノ・カネ・情報などの経営資源を活用して成果につなげていく総合的な能力のことです。
そもそもマネジメントとは、その組織やチームの成果目標を達成するために経営資源を有効活用してその組織を管理・運営する活動のことです。



マネジメントそのものについては、以下の記事をご覧ください!
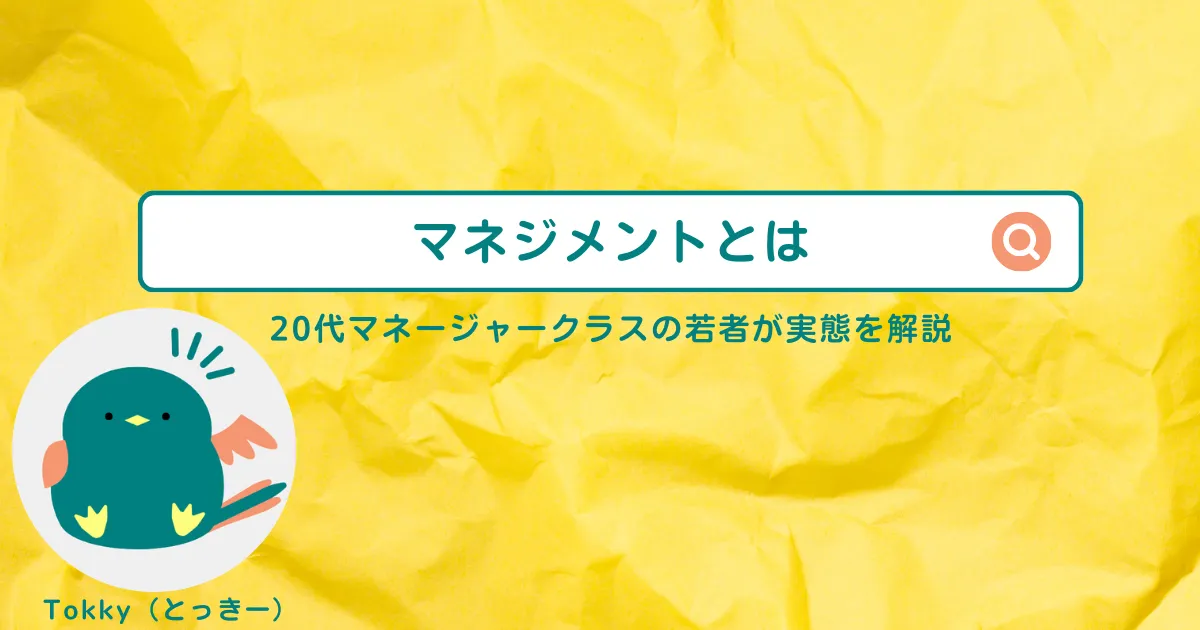
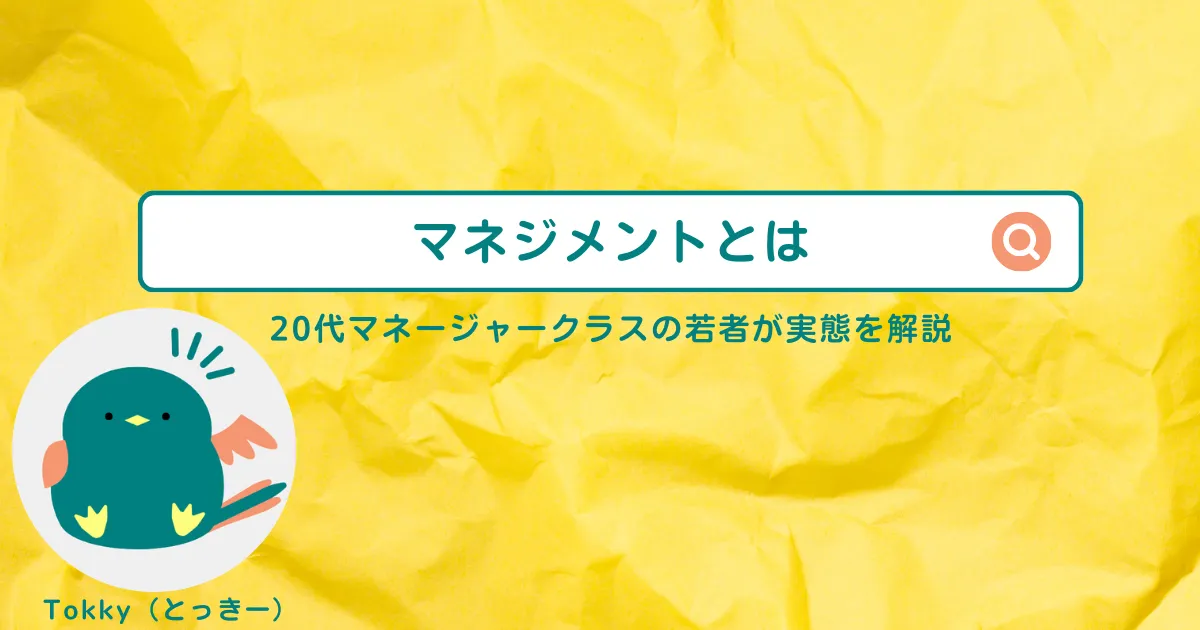
リーダーシップとの違い



他方、マネジメントスキルと聞くと、以下のようなイメージからリーダーシップを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?
- 「リーダーシップ」とは、組織を目標達成に向かってけん引するリーダーとしての資質や能力を指す。
- リーダーシップとは、組織やチームの目標達成のためにメンバーを導き、影響を与える能力のことです。
- リーダーシップとは集団をまとめ、その目的に向かって導いていく機能のことです。



確かに内容や必要となる能力で重なる部分が多いため、「マネジメント≒リーダーシップ」と連想しやすくはあります。
しかし、本来のリーダーシップとは、その組織やチームの目標および目的を達成するために他者によい影響を与えることです。



そのため、これらの行為は「リーダーシップ」そのものではなく、狭義のリーダーシップであると個人的には捉えています。
このことを踏まえると様々な要素でマネジメントスキルと違いはありますが、主に異なる点としては以下のようになります。
| マネジメントスキル | リーダーシップ | |
|---|---|---|
| 定義 | 経営資源を活用して成果に つなげていく総合的な能力 | 他者によい影響を与えること |
| 性質 | 能力 | 行動・影響力 |
| 発揮対象 | あらゆる経営資源 | 人のみ |



さらに、このあと触れていきますが、個人的見解も含めてリーダーシップはマネジメントスキルの一つとなります。
なぜなら、マネジメントにおいて人的資本を有効活用するためにはリーダーシップが必要になるためです。
実際、カッツモデルにおいてリーダーシップは、管理職に求められる3つスキルの一つであるヒューマンスキルに分類されています。



カッツモデルについては、以下をご参照ください!


マネジメントで必要なスキルまたは能力



上記の概要を前提に、普段の業務から独自に思うマネジメントに必要なスキルまたは能力は以下の7つになります。
リーダーシップ力
マネジメントにおけるリーダーシップ力とは、組織やチームの目的または目標を達成するために長期的視点で定めた方向性に沿ってメンバーの行動を促しつつ統率する能力です。



このリーダーシップ力を発揮する際に個人的に特に必要と感じる能力は次になります。
- 変革力(変化適応力/柔軟性)
- 行動力(実践力)
- 意思決定力(判断/決断力)
- 統率力
- 指導力
- 牽引力とサポート力
- 回復力(レジリエンス力)
- 人間力(責任感や誠実さ)
- 寛容力(寛容性)



そして、この能力を通じて生じたコミュニケーションでは、ファシリテーション力が求められることが多くなります。
ファシリテーション力
ファシリテーション力とは、目的ある対話や協働の場において円滑にその関係者の意見を引き出しながら合意形成を促進することによって、組織やチームにとって価値のある成果を創出する能力のことです。



この能力は、会議などの場だけでなく、目的のある対話の中で効果を発揮する能力です。よって、基本的にマネジメントでは本リーダーシップ力とセットになることが多いと個人的に感じます。
コミュニケーション力
コミュニケーション力とは、聞く力・伝える力・理解する力・共感する力など、さまざまなスキルが組み合わさった総合的な能力のことです。



コミュニケーション力には様々な要素が求められることになりますが、その中でもマネジメントでは特に次の3つが重要であると自分は感じました。
ネゴシエーション力(交渉力)
ネゴシエーション力とは、利害が異なる相手との合意を目指す話し合いを通じて双方が納得できる解決策を見つけ、長期的な信頼関係や協力関係、パートナーシップを構築する能力です。
マネジメントでは、プレゼンテーション力を通じて相手に動いてもらう力を指します。



マネジメントにおけるコミュニケーション力では、この能力が最も重要であると個人的に感じています。
プレゼンテーション力
プレゼンテーション力とは、相手の理解・共感を通じて行動を促すために自分のアイデアや情報を分かりやすく伝えるコミュニケーション力の一つです。
ヒアリング力
ヒアリング力とは、相手の話を理解するだけではなく、相手の感情やニーズ、その背景にある意図まで読み取って本質的な情報を引き出す能力のことです。
コーチング力
コーチング力とは、コミュニケーションを通じて相手の成長や潜在能力を引き出し、主体的な行動を促す能力のことです。



この能力は、主に5つのスキルと3原則から構成されています。
ちなみに、コーチングと並んで出てくる概念として、ティーチングがあります。
ティーチングとは、自分の知識やノウハウ、ある問題における答えを一方向的に教えることによって、理解を促す指導方法のことです。



もちろん、このティーチングも大切ですが、マネジメントではコーチングの方が求められる比重が大きいです。
分析力
分析力とは、ある事象や物事の分解およびそれらに関するデータや情報の収集と整理によって構造や要素間の関係性などを解明する能力です。



分析力で求められる能力は以下のようになります。
- 情報収集力
- 思考力
- 論理的思考力
- 批判的思考力
- システム思考力
- 抽象的思考力
- フレームワークの作成/使用スキル
- パソコン/ツールの使用スキル



さらに、この分析力に付随して次の3つの能力もマネジメントでは求められてきます。
アセスメント力
アセスメント力とは、自身の主観やバイアスに囚われず、客観的にある対象を公平かつ適切に評価または査定する能力のことです。
しかし、マネジメントにおいては単なる評価する能力にとどまらず、意思決定や判断といった次の行動につなげる要素まで求められてきます。
エバリュエーション力
一方、エバリュエーション力とは、ある対象や状況の効果・価値・有効性・妥当性などを客観的に正確かつ的確に評価する能力のことです。
この能力もマネジメントでは評価するだけでなく、そこからカイゼン策や次の行動の立案などを行うことまで求められます。



ちなみに、このエバリュエーションはよく介護と福祉分野で行うことが多いそうです。
モニタリング力
モニタリング力とは、ある対象の現状や変化を把握するために継続的または定期的に観察・観測・監視する能力のことです。
マネジメントでは、さらにそこから記録と分析を行い、問題の早期発見やカイゼン、修正する行動などにつなげることまで求められます。



ちなみにこのモニタリング力とアセスメント力は、介護、福祉業界だけでなく、医療や看護業界などでもよく必要とされています。
意思決定力
意思決定力とは、比較検討を通じて判断を基に出した複数の選択肢から最適な方針を主体的に責任を持って決断し、実行する能力のことです。



マネジメントでは様々な場面であらゆる要素の意思決定が求められてきますが、自身の経験的に意思決定力を構成している能力は次であると整理しました。
- 情報収集力
- 分析力
- 情報処理能力
- 思考力(コンセプチュアルスキル)
- 予期力/予測力
- 判断力と決断力
- 知識力(知識量)
- リーダーシップ力(責任感や勇気など)
- プレゼンテーション力



特に判断力/決断力や知識力は意思決定力の構成では肝になっていると個人的には感じています。
問題解決力/課題解決力
問題解決力/課題解決力とは、分析などを通じて目的や目標の達成に必要な理想的な状態と現状のギャップおよびそれが生じた原因を特定し、それらを本質的に解決・解消する能力です。



自分の普段の業務から問題解決力を分解すると次の要素になりますが、個人的には要素よりも能力内におけるプロセスが重要であると感じています。
- 情報収集力
- 情報処理能力(分析力)
- 思考力
- 予期力/予測力



そして、マネジメントでは、この能力に付随して設計・構築力も同時に求められてくることが多いです。
設計・構築力
設計・構築力とは、目的達成のために必要な要素やその構造または仕組み、プロセスなどを構想し、それらを実際に組み上げる能力のことです。



チームビルディングはこの能力とかなり関与が深い代表例の一つとして挙げられます。
テクニカルスキル
テクニカルスキルとは、カッツモデルより特定の業務に関連する知識や技術、手法などを駆使して実務を遂行する能力のことです。
そして、テクニカルスキルには主に3つの種類があります。
- 汎用スキル
- 専門スキル
- 特化スキル



テクニカルスキルの詳細は以下をご覧ください!


マネジメントスキルの身に着け方
マネジメントスキルの身に着け方に関して自分もできるように様々なことを試してきました。



もちろん今も日々新しいスキルを身に着けている最中ですが、そのような中で「これは効果的でよかったな」「こうしておいた方がよかったな」と感じた主な方法として、今回は次の4つをご紹介します。
読書を通じて知識を得る方法
まず、現在も習慣的に行っていますが、マネジメントに関する本や記事などを読んで知識を得ることはとても効果的です。
そもそも論として、マネジメントスキルを身に着ける際に、
- マネジメントとは?
- 具体的にどのような業務をするの?
- マネジメントスキルって何?
- 具体的にどのような能力が必要なの?
といったマネジメントの本質を知っておかなければ話になりません。



ゴルフを知らないのにゴルフができるようになりたいと言っているようなものです。
特に中小やベンチャー企業ではいきなり実践から入ることが多いため、事前に最低限の知識を自分で身に着けておく必要があります。



長期インターンからそのまま入社したこともありますが、自分も研修や教育など何もなしにいきなり実践から入りました。
しかし、その時にある程度の知識を持っていたことで事前にイメージを持つことができたため、めちゃくちゃ大きく変なミスをせずになんとかこなしていくことができました。



余談ですが、知識を身に着けるというのは、“事前準備をしておく”というニュアンスに近いと言えますね。
このような経験から知識を身に着けておくということは重要だと実感したのですが、知識を学んでいく際に個人的に本を通じて学ぶことがオススメです。
なぜなら、本を読むことによって知識を得るだけでなく、思考力や人間力といった能力までも鍛えることができるからです。



さらには、英サセックス大学の研究によると、6分の読書でストレスが68%程度軽減するとされています。
メンタルケアも新しいことを効率的かつ効果的に学んでいくには重要になるため、本を読んで学ぶという方法は理に適っていると言えます。
デモンストレーションを行う方法
そして、デモンストレーションを行う方法もマネジメントスキルを身に着けるうえではかなり魅力的な方法の一つだと感じました。
ぶっつけ本番のような形でいきなり実践に入ると、ハードルが高く厳しく感じることがあります。



ゴルフで例えると、打ちっぱなしを経験せずにいきなりコースに出ていくようなものです。
不慣れなことによる緊張や先が見えないことによる不安など様々な要素で心理的および身体的負荷がかかってきます。
そこで、デモンストレーションであれば、そのハードルや負荷を下げつつ安心して自分のペースで学んでいくことができます。



加えて、もちろん程度はありますが、デモンストレーションでは基本的になんでも失敗し放題であるため、その分積極的になんでも挑戦をすることもできます。
正直、自分も1回でもいいからデモンストレーションをして本番に挑みたかったなという気持ちはありました。
実践を積んでいく方法
とはいえ、振り返れば実践を積んでいくことが最もオーソドックスかつ手っ取り早い方法であると感じています。
確かにいきなりの実践はハードな面もありますが、その分それを越えられたときに得られるものは大きくなります。



デモンストレーションを多くこなして完璧にしたとしても、実践でできなければ意味はありません。デモンストレーションはあくまで練習・想定であって、実践も必ずしもその通りとは限りません。
よって、ぶっつけ本番で実践に入る方法はすぐにマネジメントスキルを身に着けられる方法であると言えます。



デモンストレーションを行う時間がないことも早く身に着けられる要因の一つですが、その分体力と精神力が必要になってきます。
よって、安定を取るなら、ある程度慣れるまでデモンストレーションを行ってそのあとはずっと実践を積むという方法が個人的経験から言うとオススメです。
組織構造を分析する方法
他方で、まだマネジメント層でないけどその層を目指している方にとっては特に、自分で組織構造を分析することも効果的と言えます。
もっと簡単かつ厳密に言えば、周りを見渡して全体像を把握していくことです。



自分は長期インターン時代に以下のような点を視ていました。
- 組織内メンバーの役割および業務内容
- 組織の指示系統と権限
- 人間関係
- 自分の給料と自分が生んだ価値の割合
- 組織(チーム)の1日と月間の売上
- 事業運営にかかっているコスト
- 事業のビジネスモデルとキャッシュフロー



もちろん、当時は全てが正確に分かるわけではなかったため、推測や推察がほとんどでした。
実際、マネジメントを実際にやってみた経験も踏まえていうと、ここでは合っているかではなく、想像することが大切となります。
なぜなら、そうすることで、分析力ももちろん、マネジメントに必要な視点や思考力を身に着けることができるためです。



実際、やり始めたときに想像と違った点や新たに知った点など色々ありましたが、その想像は大いに役に立ったと感じています。
マネジメントスキルの向上方法
身に着け方に関してお話ししてきましたが、その一方でその後のマネジメントスキルの伸ばし方も気になりますよね。



そこで、Tokkyのオススメ向上方法について、現在も続けている方法も含めた4つを今回はご紹介しちゃいます。
ドラッカーのマネジメント理論を学ぶ
現在も勉強中な部分はありますが、ドラッカーのマネジメント理論を学ぶことはマネジメントスキルの向上に大いに役に立っています。
ドラッカーのマネジメント理論とは?
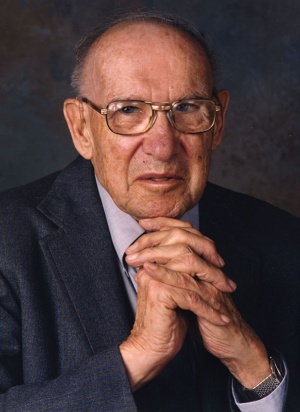
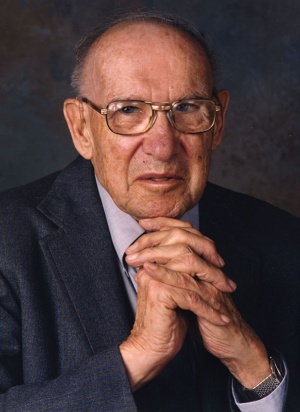
経営学者であるピーター・F・ドラッカー氏が説いたマネジメント思想のことです。



マネジメントについて学ぶ上では絶対出てくると言っても過言ではありません。
※画像引用:日経ビジネス
このドラッカーのマネジメント理論は海外ではあまり主流ではありませんが、日本ではマネジメントの父と呼ばれるくらい主流に扱われています。
その代表的な理由として、ドラッカーのマネジメント理論は日本の企業および価値観などと親和性が高いことが挙げられます。



実際、自分もそれはもかなり感じており、また内容的に実践で適用できる部分も多くあります。


行動経済学/心理学の学習
他方、行動経済学・心理学の学習もマネジメントスキルの向上に非常に効果的であると感じます。
行動経済学とは?
行動経済学とは、経済学にユーザー(消費者)視点の実際の行動から理論を形成する心理学的一面を合わせた帰納法※的学問のことです。
※帰納法とは
複数の具体的な事例や現象から、一般的な原理や理論を導き出す演繹法とは対になる思考法のことです。
Tokky(とっきー)は、
- リゼロ
- アオのハコ
- キングダム
- ヴァイオレット・エヴァーガーデン
が好きである。



Tokky(とっきー)はアニメが好きである。
この行動経済学や心理学を学ぶと、ネゴシエーション力やコーチング力などの向上が期待できます。



例えば、ラベリング効果という心理効果を用いて実際に行ったところ、次のような結果と効果がありました。
ラベリング効果
ラベリング効果とは、先に決めつけると習慣を変えるのは面倒くさいと潜在的に感じる状態に対して行動を後押しするきっかけ(ラベル・レッテル)を提供することによって、その内容に沿って行動をしてくれる効果のことです。
この効果を基に、例えば、「○○さんはメモとかマニュアルとかしっかりきれいにしているから、電話対応もすごいきれいで安心感と信頼感あるよね。」という声がけを実際に行ってみました。
その結果、その人は自主的に自身の電話対応のレベルを上げていくことができるようになっていました。



これは、ラベリングによって、「きれいで安心感と信頼感を与えるように話す」ということに意識を向けさせることができたためだと個人的に推察しています。
PDCAサイクルの徹底
これはどの分野でも言えますが、PDCAサイクルの徹底はかなり重要かつオーソドックスで王道な方法です。
PDCAサイクルとは、仮設思考※に基づいて「Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Action(改善)」を繰り返すことによって効率的かつ効果的に業務を進める施行のことです。
※仮説思考とは
目標を達成するために仮説を指す仮の結論を立て、それに基づいて情報収集や検証、修正を行うロジカルシンキングの一つを指します。



人によって、Action(改善)をAdjust(調整)とすることもありますが、個人的にPDCAサイクルの中で特にC(検証)とA(改善(調整))の部分がかなり重要だと感じています。
特にコーチングをする際も含めてよく見受けられるものとして、
- Plan(計画)だけして何もしない
- Do(実行)だけやって終わりにしてしまっている
- C(検証)とA(改善(調整))をしないことから
- 同じ過ちを繰り返す
- 成長しない
などということがあります。



よって、スキルを向上させる上でPDCAサイクル、特にCAの部分の徹底は欠かせないと言えます。
上司や他の人をマネジメントしてみる
最後に、上司や他の人をマネジメントしてみるという方法も実は効果的です。



上司や他の人をマネジメントするってどういうこと?って思いますよね。
これは、
ということです。



実は、ここ最近で次のようなドラッカーのマネジメント理論をヒントに自分で展開した視点および方法です。
「成果をあげるためには、上司の強みも生かさなければならない。」
「上司に認められ、活用されることによって、初めて自らの貢献に焦点を合わせることが可能となる。」
引用:『プロフェッショナルの条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】



マネジメントというと自分より下の者に対して行うイメージが強いかと思いますが、そんなことはないということです。
実際、自分も基本的に自分より年上の社会人経験が長いパートさんのマネジメントを行っています。
このことも踏まえて、上司や他の人を動かすということもマネジメントの一種だと思ってやるとそのスキルの向上が図れます。
【要約】この記事のQ&A



読んでくれた方はお疲れ様でした!
ここまでの内容を、Q&A方式でまとめました!
まとめ|実際のマネジメントで必要なスキルは主に7つ!



自分の普段の業務を基から個人的にマネジメントに必要なスキルは大きく分けて7つあるとしました。
そして、実際に自分が行った方法からそのスキルの身に着け方や伸ばし方についてもお話ししました。
この身に着け方と伸ばし方に関して総括すると、
という方法が最適であると言えます。



しかし、「今の会社だとなかなか実践を積ませてくれないんだけどその場合はどうすればいいの?」と疑問に思う方もいるかと思います。
すぐマネジメントを始めたいなら管理職への転職が早い
そんな場合は、ハイクラス転職で管理職部門に転職することが一番よいです。
- 「早くキャリアアップして成果を出したい!」
- 「でも今のままだとあまり臨めなさそう…」
- 「いつそんな話が来るのかな…」



そうやって、無理に今の会社に自分を合わせて機会が来るまで待っていませんか?
結論、そんな風に待っている必要はありません。
もし、その待っている時間で管理部門に転職して実践を積んでいけた場合の自分のキャリアや年収を想像してみてください。



もったいないと思いませんか?
でも、
- 「管理職への転職って難しいんじゃないの?」
- 「面接の対策ってどうすればいいの…?」
- 「求人数少なそう…」
って不安になりますよね。



そんなときは基本的に全て無料でサポートをしてくれる専門の方にぜひ相談してみましょう!
\ 管理系職種の転職支援実績第 1 位/