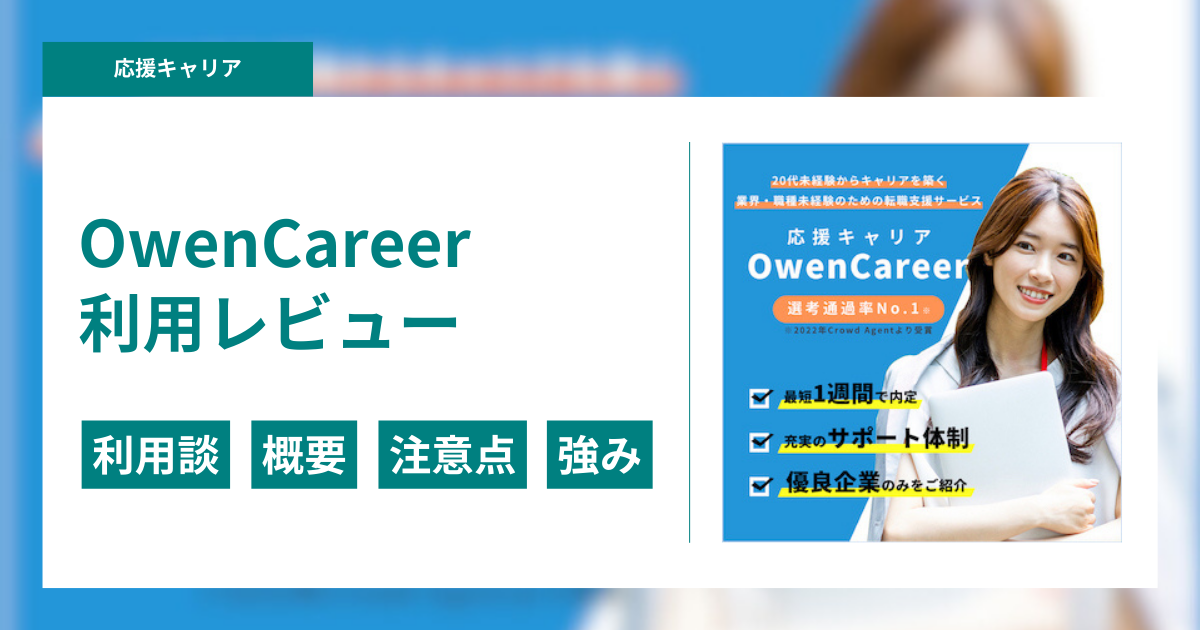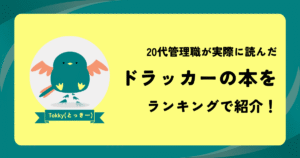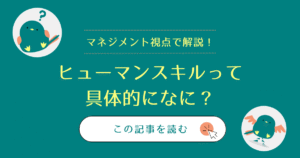この記事でわかること
- マネジメントスキルとは
- カッツモデルの概要
- 現代におけるカッツモデルの活用例
- カッツモデル活用によるメリット
- キャリアアップで管理職を目指すために必要なこと
この疑問に関して、それは主に3つあると1955年にロバート・L・カッツ(Robert L. Katz)という人物がカッツモデル(カッツ理論)を用いて提唱しました。
 Tokky(とっきー)
Tokky(とっきー)マネジメントや管理職って聞くと、優秀な成績を収めた人が昇進して行っているイメージがありませんか?
多少の外部要因はありますが、学生時代における部活や日本企業の特徴である年功序列や終身雇用などからこのようなイメージを抱く人は多いです。
しかし、実際では、プレイヤーとして優秀だった人がそのままキャリアアップして管理職になった途端、優秀でなくなってしまったという話があります。
似た例で、スポーツにおいてめちゃくちゃうまい選手がキャプテンをやったけどチームをまとめきれなかったという話もあります。
逆に、プレイヤーとしては目立った成績や実績がなかった人がキャプテンや管理をしたら優秀だったという場合もあります。
このことから、一部の部活動では、統率力が高いことから試合に出ていない選手がキャプテンを担っているというチームもあります。



つまり、プレイヤーとして必要なスキルや能力は、マネジメントで求められるものとは異なるのです。
そのような背景を踏まえて、今回は、カッツモデル(カッツ理論)を基にマネジメントに求められるスキルや能力に関してお話ししていきます。
マネジメントスキルについて
マネジメントで必要なスキルや能力について具体的なお話をしていく前に、マネジメントスキルや能力そのものの定義について定めていきます。



「マネジメント」の定義については、以下の記事を参照してみてください!特に、「トップマネジメント」「ミドルマネジメント」「ロワーマネジメント」の3つの概念は今回のお話では重要項目です!
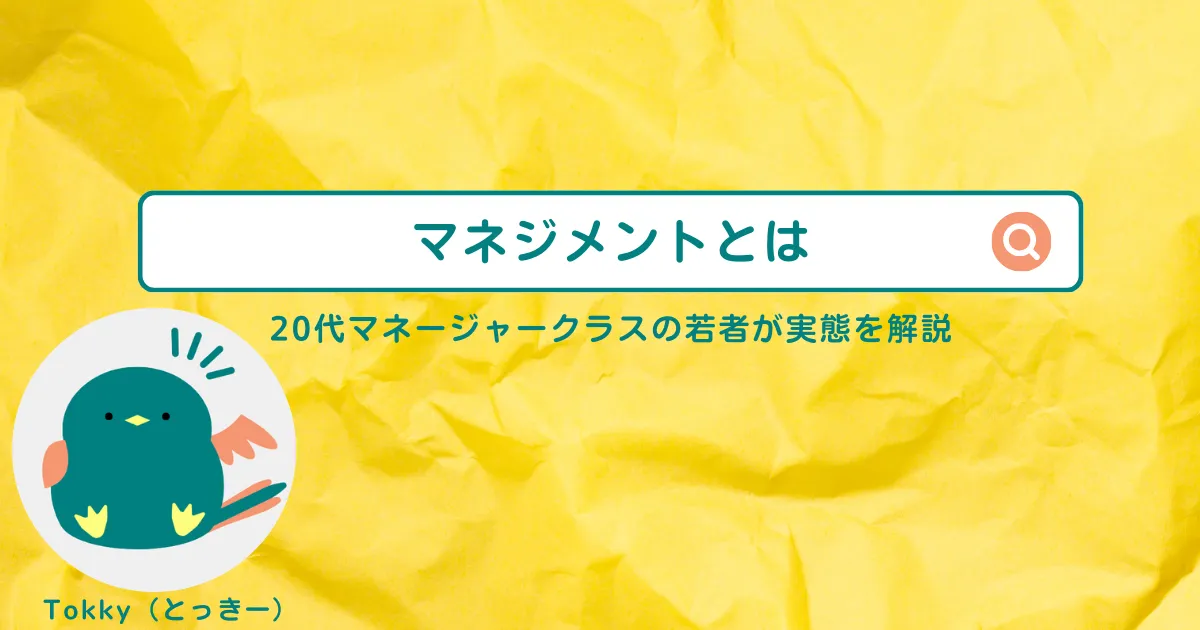
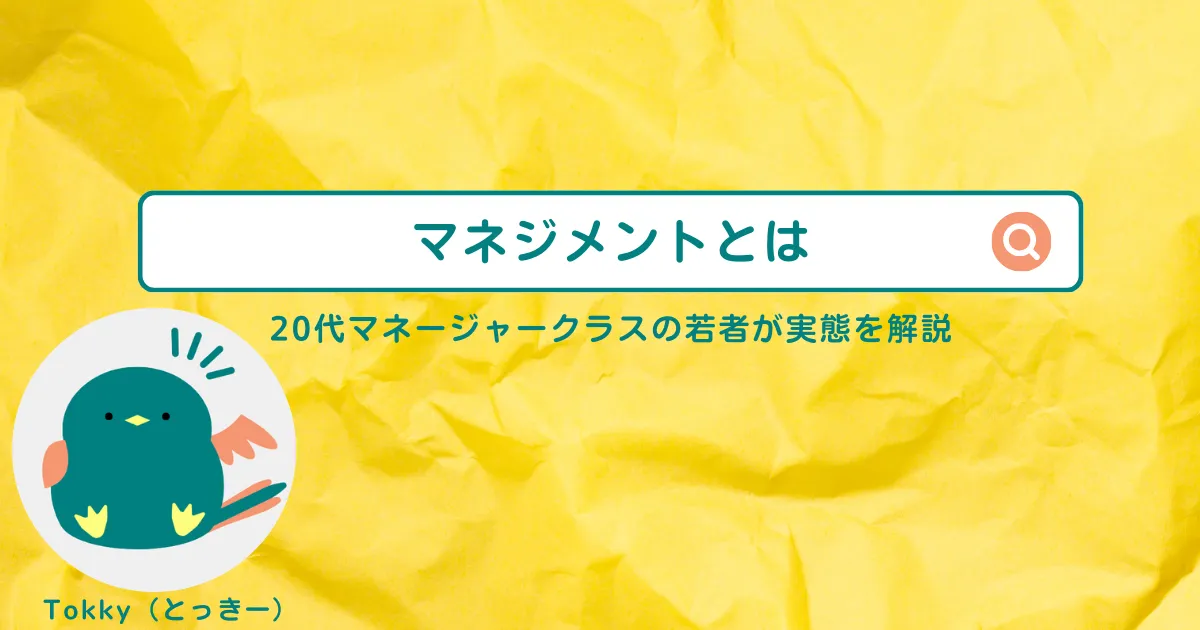
マネジメントスキルとは
カッツモデル(カッツ理論)から、自分が独自に思うマネジメントスキルとは、
のことです。



“管理職=その会社で優秀な人”というイメージから、生まれつき突出したものがあるのではないかと思いませんか?
そこから、自分には秀でた才能や素質なんてないから管理職とか向いていないのでは…と思ったこともありませんか?
結論、そんなことはありません。
マネジメントスキルは生まれつき持っている才能や素質から備わるものではなく、学習や経験などを通じて身につけることができる能力です。
よって、基本的に正しく学んでいけば誰でも習得できるスキルであるため、誰でも管理職を目指すことができます。
リーダーシップとの違い



マネジメントスキルと聞くと、リーダーシップを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?
このあと改めて触れていきますが、リーダーシップとは、その組織やチームの目標および目的を達成するために他者によい影響を与えることです。
そして、カッツモデルにおいて、このリーダーシップはマネジメントで求められる要素の一つとして含まれています。



つまり、「マネジメントスキル=リーダーシップ」ではなく、「マネジメントスキル⊃リーダーシップ」となります。
カッツモデルの概要
ここから、本題でもあるロバート・L・カッツが1955年に提唱した「カッツモデル(カッツ理論)」について解説していきます。
カッツモデルとは
カッツモデルとは、役職に応じて管理職に求められる3つのスキルのバランスが変化することを示した理論です。
.webp)
.webp)
カッツモデルでは、管理職における役職を上から以下のトップ・ミドル・ロワーの3つ分けています。



現代でも残っているこのマネジメント階層の分け方は、実はカッツモデルが論理的に表した考えだったのです。
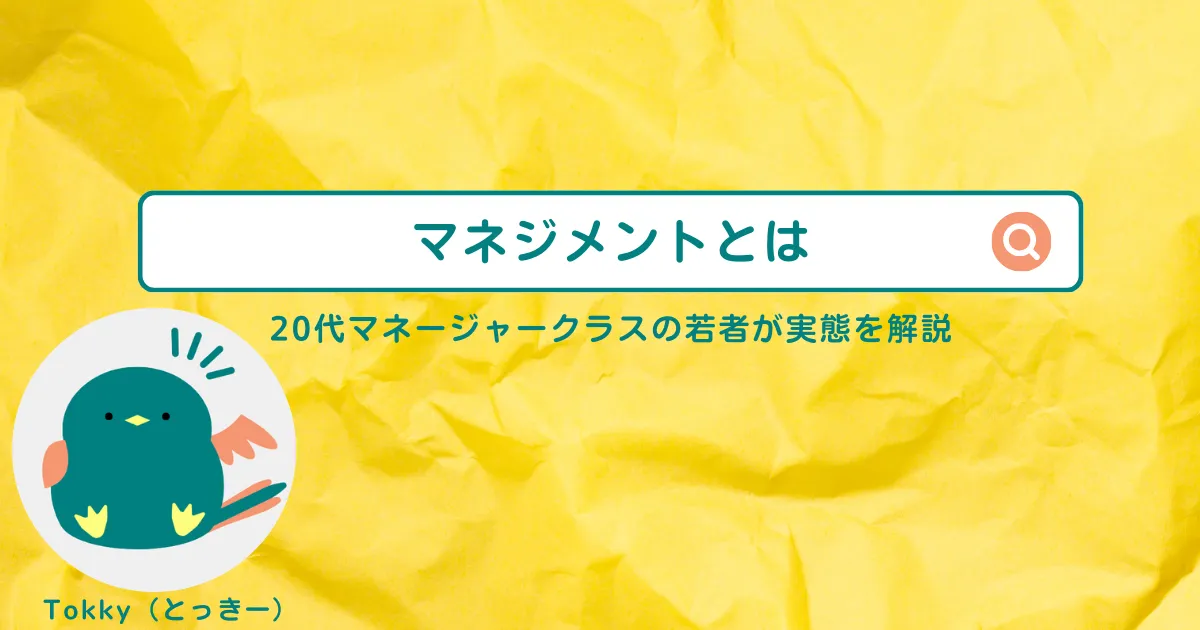
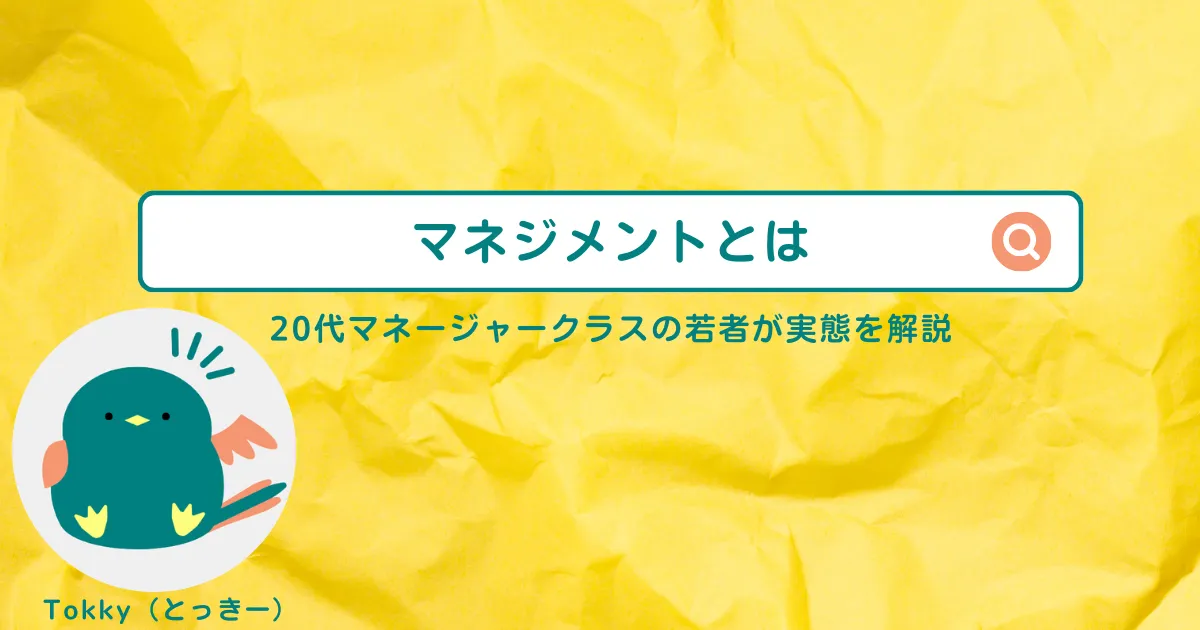



ここでは主にカッツモデルを構成している各3つのスキルについて、詳しく見ていきます。
テクニカルスキル
はじめに、カッツモデルにおけるテクニカルスキルとは、特定の業務に関連する知識や技術、手法などを駆使して実務を遂行する能力のことです。
現代におけるテクニカルスキルは、次の3種類に分類されています。
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| 汎用スキル | テクニカルスキルにおいて職種や業種を問わずさまざまな実務に共通して求められる基礎的な土台となるスキル |
| 専門スキル | 特定の業務を遂行するにあたってその業界または職種では標準的な知識や技術等 |
| 特化スキル | 専門スキルの高度化および応用によってさらなる付加価値を生み出す独自性の高いスキル |
このスキルは、ロワーマネジメントほど重要度が増し、トップマネジメントほど重要度が下がっていきます。
ロワーマネジメントにとって重要な理由は、現場や現場のタスクを管理することからその実務をしっかり把握してできるようにしていなければならないためです。
時と場合によってはロワーマネジメントも実際に現場に入るため、そもそもこのスキルを実際に持っていないと話になりません。
一方、トップマネジメントにとって重要でない理由は、組織全体のビジョンやミッション、戦略などを策定して全体的な方向性を示す業務と役割を主に担うためです。



詳細は以下の記事でお話ししています!


ヒューマンスキル
次に、カッツモデルにおけるヒューマンスキルとは、コミュニケーションを取りながら他者と協力して集団の中で円滑に活動できるための関係性を築く能力のことです。



簡潔に言い換えれば人間力や社会性のことです。
ちなみに、ここにおける他者は、外部と内部双方を含む組織関係者を指しています。
現代における主なヒューマンスキルの例として、以下があります。
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| リーダーシップ力 | その組織やチームの目標および目的を達成するために他者によい影響を与えること |
| ファシリテーション力 | 目的ある対話や協働の場において円滑に参加者の意見を引き出しながら合意形成を促進することによって、組織やチームにとって価値ある成果を創出する能力 |
| コミュニケーション力 | 聞く力・伝える力・理解する力・共感する力など、さまざまなスキルが組み合わさった総合的な能力 |
| ヒアリング力 | 相手の話を理解するだけではなく、相手の感情やニーズ、その背景にある意図まで読み取って本質的な情報を引き出す能力 |
| プレゼンテーション力 | 相手の理解・共感を通じて行動を促すために自分のアイデアや情報を分かりやすく伝えるコミュニケーション能力の一つ |
| ネゴシエーション力(交渉力) | 利害が異なる相手との合意を目指す話し合いを通じて双方が納得できる解決策を見つけ、長期的な信頼関係や協力関係、パートナーシップを構築する能力 |
| コーチング力 | コミュニケーションを通じて相手の成長や潜在能力を引き出し、主体的な行動を促す能力 |
| 向上心 | 与えられた成果目標、またはそれより自分で設定した高い基準を達成するために必要な自己資源を成長させたいという内発的動機に基づいた志向性 |
※これは一部の例です。
カッツモデルにおいてこのスキルは、求められる種類の内容や比重は多少異なりつつも全てのマネジメント階層で重要なスキルとなっています。



しかし、皆さんの中には人間性や社会性がない方が成功を収めていると聞く人もいるのではないでしょうか?
(ちなみに、自分はそんな話を聞いたことがあります。)
これについてカッツモデルから考えると、彼らにもヒューマンスキルがあると言えます。
そのため、疎かにしていいというわけではなく、むしろドラッカーによればマネジメントにおいてヒューマンスキルは何よりも大切であると述べています。



ヒューマンスキルの詳細は以下の記事を確認してみてください!
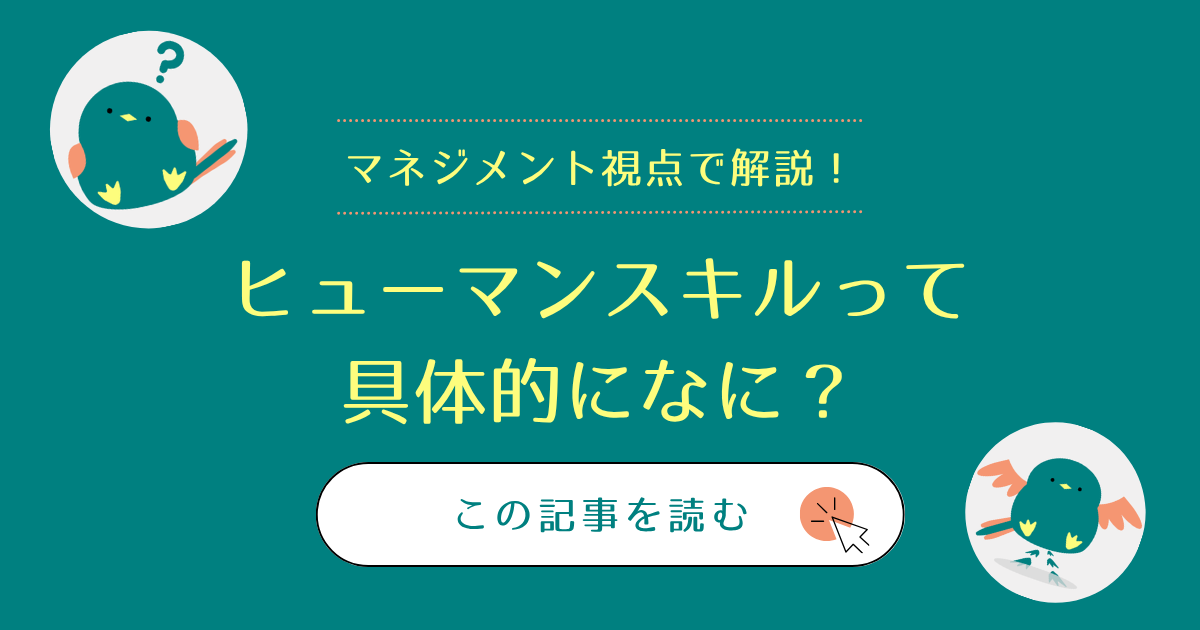
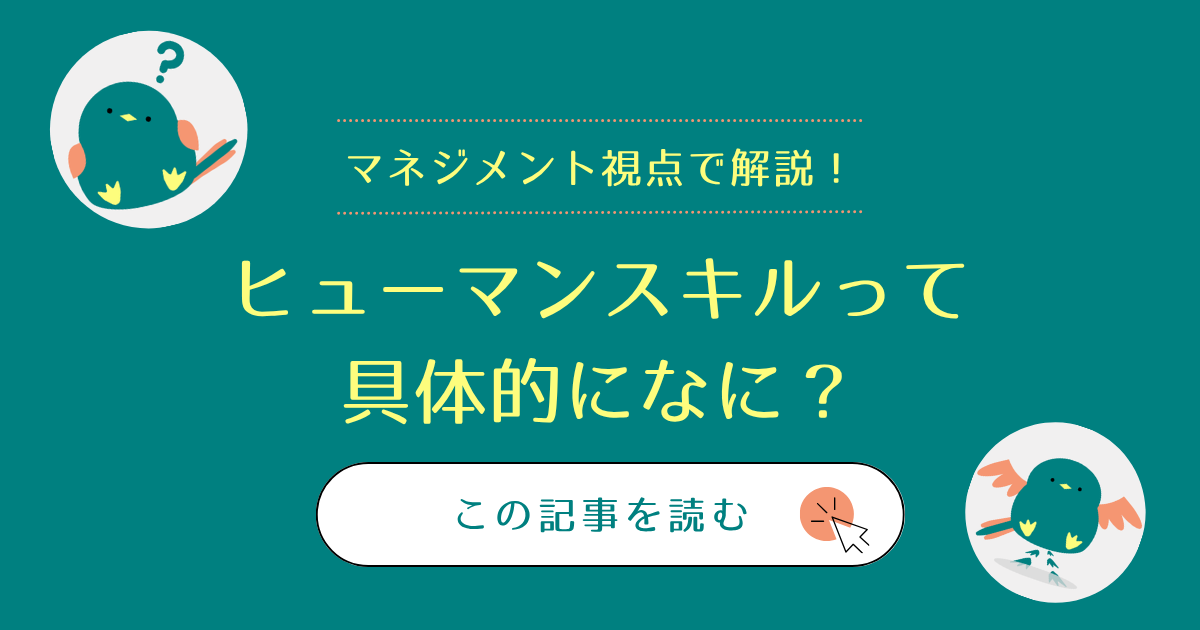
コンセプチュアルスキル
最後に、カッツモデルにおけるコンセプチュアルスキルとは、全体を俯瞰しながらあらゆる物事の本質を捉えて適切な判断や戦略的な意思決定などを行う概念化能力のことです。
テクニカルスキルとは理由も対照的に、このスキルは、トップマネジメントほど重要度が高く、ロワーマネジメントほど重要度が低くなっています。
現代におけるコンセプチュアルスキルの代表例には、以下の能力が挙げられます。
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| 抽象的思考力 (アブストラクトシンキング) | ある物事を一部分ではなく俯瞰して視ることでそれの本質を捉え、またそこから一般的な原則や理論、概念などを導き出す能力 |
| システム思考力 (システムシンキング) | 一部の事象に目を奪われず、各要素間の相互依存性や相互関連性を把握して全体的な構造やその動きを捉える能力 |
| 戦略的思考力 (ストラテジックシンキング) | 長期的な視点から物事や未来の展望と変化、機会などを捉えて最適な戦略を立案・実行する能力 |
| 論理的思考力 (ロジカルシンキング) | ある物事を筋道立てて考えることや体系的に整理することなどによって矛盾がない一貫性のある結論を導き出す能力 |
| 垂直思考力 (バーティカルシンキング) | 論理的に一つの方向に深く掘り下げながら正しい答えを導く能力 |
| 批判的思考力 (クリティカルシンキング) | 前提や根拠などを疑いながらある物事を鵜呑みにせずに客観的または論理的かつ多角的な視点で考える能力 |
| 創造的思考力 (クリエイティブシンキング) | 既存の常識や固定概念にとらわれず、論理的に新しい発想でアイディアや価値を生み出す能力 |
| 水平思考力 (ラテラルシンキング) | 創造的思考とは異なって論理的に考えすぎず、突飛的または飛躍的な発想でアイディアや価値を生み出す能力 |
※これは一部の例です。
これより、冒頭でお話した例が起きる要因として、このコンセプチュアルスキルの有無またはそのレベルの洗練度などが挙げられます。
あるいは、組織内における自身のポジティブでこのスキルを含めた3つのスキルのバランス悪さからうまく発揮されていないことも要因として言えます。



コンセプチュアルスキルについての詳細を知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください!


カッツモデルが提唱された背景
カッツモデルが提唱された1955年のアメリカでは、第二次世界大戦後による経済成長から様々な変化や発展が起こっていました。
産業構造の変化
まず、技術革新による機械化から大量生産・大量消費社会になったことに伴い、特に自動車産業や家電産業などの製造業と石油化学産業が急成長を遂げました。
そして、経済や産業の急成長による賃金上昇に伴って中産階級も成長し、家電製品や自動車などの耐久消費財が普及していきました。
このことによって、郊外化(サバーブ化)※や、家庭における生活スタイルなどの大きな変化などが起こりました。
※郊外化(サバーブ化)とは
都市中心部から外れた郊外地域への人々の移住によって、その地域に都市的要素と農村的要素が混在するようになる変化のプロセスです。
加えて、このような現象は、以下のようなサービス業の成長ももたらし、またその結果として産業の中心はサービス業へ移行していきました。
- 金融業
- 不動産業
- 教育やヘルスケア
- 小売業
- 飲食業
- 広告業
- 娯楽産業
労働市場の変化
産業構造の変化に伴って、労働市場ではホワイトカラー※が増加し、ブルーカラー※の割合が相対的に減少していきました。
※ホワイトカラー&ブルーカラーとは
- ホワイトカラーとは
-
主に事務職や管理職、専門職などの知的または専門的なオフィスワーク業務を行う労働者の総称です。
- ブルーカラーとは
-
主に製造業や建設業、運送業、整備業などで肉体的労働または物理的な作業を行う労働者の総称です。



現代のアメリカの労働市場の特徴は、この時代から形成され始めたものと言えます。
そして、戦争によって男性労働者が戦場に動員されたことで女性は労働する機会が増えましたが、戦後も職場に残ったことで女性労働者が増加しました。
他方で、1950年代前半ではこのような変化や社会的情勢、労働需要の高さなどから労働組合の影響力が強かったとされています。
そのため、当時は、労働条件や賃金などにおける企業側の交渉が難しくなっており、また問題視されていました。
企業の大規模化
経済成長による産業の急成長に伴って多くの企業も急速に拡大し、例えば自動車産業におけるビッグスリーなどの大規模な組織が台頭し始めました。
- ゼネラル・モーターズ(GM)
- フォード(Ford)
- クライスラー(Chrysler)
この企業拡大は、分業化や組織の階層化などによる専門化や組織の複雑化などをもたらしました。
さらに、産業構造や労働市場も変化したことで、単なる作業遂行ではなく、労働者に協力や適応などといった多様な役割を企業は求めるようになりました。
このようなことが相まって、管理職に求められるスキルやマネジメントが高度化し、またその重要性は増していきました。
一方で、このような変化に対応するために、企業は管理者の育成をする必要が出てきました。
経営学・組織論の発展
産業構造や労働者の変化、企業の大規模化も含めて、以下のような経営学や組織論の発展の流れからカッツモデルは提唱されました。
そのため、カッツモデルはファヨールの管理過程論を軸に主に3つの理論の影響を受けて提唱された理論であると推察されています。
1911年にF. W. テイラーが提唱した科学的管理法とは、調査や分析などによる作業の標準化や課業※によって生産性や効率性を向上させる管理手法のことです。
※課業とは
1日に標準的な作業量や達成すべきノルマ、タスクのことです。
しかし、この管理手法では、管理の合理化・科学科に伴う労働者の疎外や抑圧が問題提起されました。
この問題提起を基に、1927年、1924年から1932年にかけて行われたホーソン実験から人間関係論が誕生しました。
人間関係論とは、非公式組織※の側面への注目と働きかけによる従業員のモラール(勤労意欲)の向上から結果的に生産性や効率性を向上させる理論の総称のことです。
※非公式組織とは
正式な命令系統や組織図に表れない人間関係や自然発生的なグループのことです。
他方、ホーソン実験とは、メイヨーとレスリスバーガーが主導したアメリカのホーソン工場で行われた実験のことです。
この実験から、作業能率を決定するのは労働条件ではなくモラールであり、またモラールは非公式組織の影響を受けることが明らかになりました。



人から注目されていると認識することでパフォーマンスや能力などが向上する心理現象も判明しました。
この効果はホーソン効果と言われています。
一方で、1938年には、チェスター・バーナードが『経営者の役割』を発表しました。
この著書において、まず組織はコミュニケーション(意思疎通)・貢献意欲(協働意欲)・共通目的の3要素によって成立するとしています。



ちなみに、この3要素は公式組織の3要素と言われています。
そして、組織の存続にはこれら3要素の確保が必要であることから、管理を組織の維持・拡大の機能であると捉えました。
具体的には以下の3つを管理の基本的な機能とし、またこの3つの機能を果たすことが経営者の役割であるとしました。
- 組織の目的達成のための専門化の革新
- 組織構成員の動機満足と貢献意欲の確保のための適切な誘因の提供
- 伝達確保のためのオーソリティの確立
加えて、このような管理の諸機能に共通する要素は意思決定であり、またそれが管理の本質であるともしました。
さらに、この意思決定には次の2つの側面があり、リーダーシップの本質はそのうちの一つである道徳性の創造であると述べました。
- 環境適応を目指してなされる機会主義の側面
- 組織構成員に行動準則を与える道徳性の側面
一方で、戦後における様々な変化や発展によって、1916年にファヨールが提唱された管理過程論が再評価されました。
この理論において、企業の経営活動(職能)は6つあり、そのうちの一つかつ重要なものとして管理的活動(職能)があるとしました。
そして、自身の経営経験から14の管理原則と、管理を5つの機能(要素)の円環プロセスとみなすことをファヨールは述べました。



各理論の詳細はまた別記事で紹介します!
学問・教育の発展
経営学や組織論だけでなく、心理学や行動理論などの分野も急速に発展していきました。
リーダーシップ理論において、当初は“リーダーには生まれ持ったカリスマ性や知性などの資質がある”という特性理論※が主流でした。
※特性理論とは
様々な状況において現れる誰もが持つ行動傾向のことである特性をその人がどのくらい持っているのかという量で分類しようとする考えです。
その理由は、“優れたリーダーは生まれつきリーダーとしての才能を持つ”という考え方が根強かったためです。
しかし、優れたリーダーに共通する決定的な特性が見つからなかったため、1950年代に入るとこの考えの限界が指摘されるようになりました。
そして、特性ではなく特定の行動によってリーダーシップは発揮されるものであるとする行動理論が発展していきました。
このような背景や管理者育成の必要性が出てきたことから、次のような考え方が注目され、またその認識が広がっていきました。
加えて、この行動理論の発展は、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)をはじめとするアメリカの大学でマネジメント教育を発展させました。



このことに伴って、「管理職にはどのような能力が必要か?」という議論が活発になり、この流れの中でカッツモデルが登場したのです。
※タップかクリックで詳細を確認できます



このようなアメリカ経済の変化や発展に伴う企業組織の変化や発展に対応するためにカッツモデルが生まれました。
カッツモデルの企業における活用例



しかし、1955年に提唱されたことから「古いから現代では使えないし、意味ないんじゃないの?」と思った方はいませんか?
カッツモデルにおける企業組織の構造は現代とほぼ同じであるため、そんなことはありません。
実際に、現代でも次の3つの場面で主に活用されています。
評価項目・評価基準の設定
まず、現代において、役職または各マネジメント階層に求める評価項目やその基準の設定で主に活用されています。
カッツモデルが提唱された背景の一つとして、労働組合の影響力の強さによる労働条件や賃金などにおける企業側の交渉の難しさが問題視されたことがあります。
しかし、カッツモデルの誕生によって、労働組合との関係を円滑に保ちつつ効果的に企業が交渉を進められるようになりました。
このことから、現代でも評価項目やその基準を設定する際にカッツモデルが活用される場面が見受けられます。



さらに、この評価項目や基準のウエイトの調整によって人を動かすことや、スキル診断ツールとしても活用されています。
研修・人材育成
評価制度に関する活用に伴い、役職や各マネジメント階層における必要かつ効果的な3つのスキルに応じた研修の実施や人材育成の面でも活用されています。
カッツモデルが提唱された背景の一つとして、様々な変化によって管理者を育成する必要が出てきたことがあります。



つまり、カッツモデルは育成することを考慮されてできた理論であると言えるため、人材育成や研修でも活用することができるのです。
現代における研修は大きく分けてOJTとOFF-JTの2つに分けられ、さらに細かく分類すると6つの種類に分けられます。
- OJT(On the Job Training)
-
職場における実務を通じて知識や技術などを指導していく職場内訓練とも呼ばれる研修方法のことです。
- OFF-JT(Off the Job Training)
-
業務から離れて行う研修や学習全般を指す職場外研修と呼ばれる研修方法のことです。
そして、OFF-JTは、主に以下の4つに分類することができます。
- eラーニング
-
インターネットやデバイスを通じて行う学習や研修を行う方法のことです。
- ワークショップ
-
参加・体験・協働型講座を通じて学習や研修を行う方法のことです。
- 外部研修・セミナー
-
社外の企業や専門家への委託や開催されているイベントを通じて研修を行う方法のことです。
- 自己啓発支援
-
企業や組織が従業員の自主的な学習や能力開発を支援する方法のことです。
このことを踏まえて、評価項目や基準、スキル診断ツールなどを基に各3つのスキルの習得または育成のために以下のような研修が実施されています。
| 各マネジメントスキル | 具体的な研修例 |
|---|---|
| テクニカルスキル | OJT・eラーニング・実技研修・ロールプレイングなど |
| ヒューマンスキル | コミュニケーションの傾向診断・マナー講習・チームビルディング研修・問題解決型ワークショップ・360度フィードバックなど |
| コンセプチュアルスキル | ビジネス戦略講習・クリティカルシンキング研修・ビジネスシミュレーション研修・ケーススタディなど |
人材管理・人材採用
他方で、評価に関する活用から、組織内における人材の適切な配置を考える人材管理の面でも活用されています。
なぜなら、評価項目や基準から誰をどのような階層やポジションに配置するのが適切なのかを効率よく論理的に考えることができるためです。



これより、昇給基準の設定でもカッツモデルを活用することができるというわけです。
さらに、このことに付随して「どのようなスキルがよくて、逆にどのようなスキルが足りていないか?」といった分析もできます。
そのため、「どのような人がいいのか?」「採用要件は?」などといった人材採用の面でも活用することができます。
カッツモデルを活用するメリット
カッツモデルの活用は、組織や管理者、従業員に様々なメリットをもたらします。
組織にとってのメリット
組織にとってのメリットは、体系的な人材育成や明確な評価制度ができることなどから組織全体における業務や活動の効率性が上がることです。
評価制度の明確化
3つのスキルを基に評価軸を設定することから、評価制度を明確化させることができます。
そして、評価制度の明確化は、公平性・納得感のある評価制度の整備へとつながります。
適材適所の実現
評価制度の明確化によって適切な人材配置ができるため、それに伴って業務効率や成果を向上させることができます。
人材育成の体系化
評価制度の明確化に伴う育成計画やカリキュラムの体系化によって、研修や人材育成の生産性・効率性も向上されます。
マネジメント階層別のスキル強化
人材育成の体系化による生産性・効率性の向上に伴って、各マネジメント階層に必要な3つのスキルの強化を図ることができます。



そして、スキル強化は組織全体のバランスを整えてくれるため、より効果的で効率的な組織運営の実現をもたらします。
管理者にとってのメリット
管理者にとってのメリットは、管理職に求められるスキルを体系的に整理できるため、マネジメント業務の効率が向上することです。
自身のマネジメントスキルの把握
カッツモデルによって、自分のマネジメントスキルを俯瞰的に理解及び把握することができます。
そして、そこから分析していくことによって、自身でそれらを強化していくこともできます。
マネジメント力の向上
評価制度を基にしたチーム内のスキル構成を見ながら、適切な役割分担や関係を作ることができます。
加えて、階層ごとに必要なスキルを意識した育成や評価が行えるため、チームビルディングで有効的な一面を発揮します。
さらに、人材管理では、採用から育成、評価、配置までの全プロセスに一貫性をもたせることができます。
メンバーへの教育の質の向上
自身のマネジメントだけでなく、メンバーのスキル傾向も把握しやすくなります。



そのため、メンバーの成長や状況に応じた適切な指導やフィードバックが可能となります。
キャリアの見通しが立つ
自分やメンバーがさらに上の階層に上がるために強化すべきスキルを把握することができます。



これより、効率的なスキル強化をしていくこともできるようになります。
従業員にとってのメリット
従業員にとってのメリットは、評価軸の透明性から自身が目指すキャリアや目標が明確になることが挙げられます。
評価軸の透明性
評価されるポイントやスキルが分かりやすいため、評価に対する公平性や納得感を感じられやすいことがあります。
そのため、労働意欲やモチベーション、成長意欲が刺激され、またそれらの向上をもたらします。
目指す目標や方針の確立
公平性や納得感が高い評価から、自分がどのスキルを強化していくべきなのかといった目標や方針が確立しやすくなります。
スキル強化のしやすさの向上
さらに、評価軸の透明性や、目指す目標や方針の確立によって、効率的に自身のスキルを強化していくことができます。
キャリア形成への活用
一方で、将来どのようなポジションやキャリアを目指すのかといったキャリア形成への活用も期待できます。
まとめ|マネジメントで必要なスキルとは?
カッツモデルは1955年に提唱されましたが、現代でも企業における人材育成や評価制度で活用されています。
これより、冒頭に挙げた「マネジメントに必要なスキルや能力ってなに?」という質問の回答は、
- テクニカルスキル
-
特定の業務に関連する知識や技術、手法などを駆使して実務を遂行する能力
- ヒューマンスキル
-
コミュニケーションを取りながら他者と協力して集団の中で円滑に活動できるための関係性を築く能力
- コンセプチュアルスキル
-
組織全体を俯瞰しながらあらゆる物事の本質を捉えて適切な判断や戦略的な意思決定などを行う概念化能力
の3つのスキルとなります。
つまり、管理職を目指す方やキャリアアップをしたい方、マネジメントをやりたい方はこの3つのスキルを持っている必要があります。
しかし、それは現時点である必要はなく、また全スキルを満遍なく持っていなければいけないわけでもありません。
自身が目指す役職や階層によって必要なスキルのバランスは異なり、また学習や経験、研修などを通じて習得していくことができます。



このカッツモデルを参考にすれば、今の自分には何が足りないのか、何をしていくべきなのかが見えてきます。
ぜひ参考にしてみてください!